
【2025年・令和6年度補正】事業承継・M&A補助金の対象と申請方法(11次公募)
事業承継・M&A補助金とは?活用方法によっては費用負担を大きく軽減できる可能性があります。2025年度を基に制度の概要と特徴を詳しく解説しますので、公募要領を理解し、自社が対象となるか確認してみてください。


【2025年・令和6年度補正】事業承継・M&A補助金の対象と申請方法(11次公募)

「後継者不在のためM&Aを検討しているが、専門家への依頼費用の負担が重い」「事業拡大のために企業買収を進めたいが、デューデリジェンスなどのコストを抑えたい」などの悩みを抱える経営者やM&A担当者の方は多いのではないでしょうか。
実は、「事業承継・M&A補助金」を活用すれば、これらの費用負担を大きく軽減できる可能性があります。この補助金は、M&Aプロセスで発生する専門家への手数料や調査費用の一部を国が補助する制度です。
本記事では、令和6年度補正予算として2025年に実施された事業承継・M&A補助金(第11次公募)の公式情報に基づき、制度の概要から対象経費、具体的な申請方法、採択のポイントまでを網羅的に解説します。
この記事を最後まで読めば、補助金を活用してコストを最適化し、円滑なM&Aを実現するための具体的な知識が身につき、次の一歩を踏み出すことができるでしょう。
まずは最新の公募要領を理解し、自社が対象となるか確認してみてください。

事業承継・M&A補助金とは?制度の概要と特徴
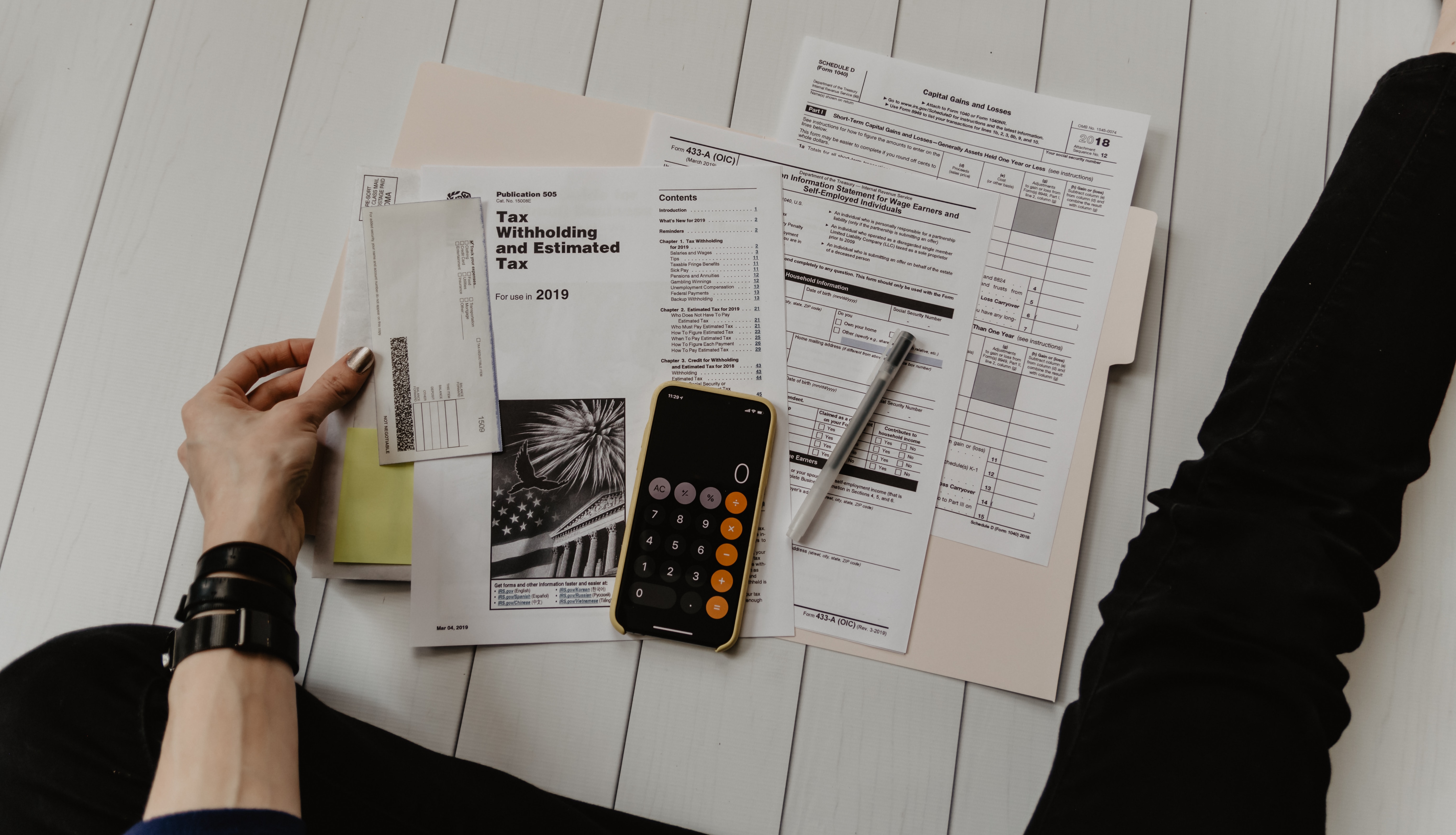
事業承継・M&A補助金は、中小企業庁が所管する制度で、事業承継やM&Aを進める中小企業を支援する目的で設けられています。正式名称は「事業承継・引継ぎ補助金」で、後継者不在の解消や、M&Aによる成長を目指す企業を支援し、経営資源の散逸を防ぐことが目的です。
2025年に実施される令和6年度補正予算の公募では「専門家活用型」が中心です。M&Aに必要なファイナンシャルアドバイザー(FA)や仲介業者の手数料、デューデリジェンス(DD)費用などの専門家経費が補助対象となります。
この補助金の最大のメリットは、M&Aに欠かせない専門家の支援を、低コストで受けられる点です。
これにより、M&Aの計画から実行、統合後のPMIまでを円滑に進めやすくなり、事業の継続や成長を支える効果が期待できます。
事業承継・M&A補助金とは?制度の概要と特徴
令和6年度補正予算に基づく事業承継・M&A補助金は、第11次公募として実施されました。
本記事では、公表された第11次公募の公式情報をもとに、申請スケジュールや支援対象、制度の特徴をわかりやすく解説します。
今後の公募に備えるためにも、最新の情報を正確に把握しておきましょう。
第11次公募のスケジュール
第11次公募のスケジュールは、中小企業庁の公式サイトで公表され、以下の日程で実施されました。
【第11次公募スケジュール(実績)】
・公募期間: 2025年5月9日(金)~ 2025年6月6日(金)17:00
・採択通知:7月上旬頃/交付決定:7月中旬頃
・事業実施期間: 交付決定日〜2026 年7月11日
・実績報告期間: 7月以降順次
申請は既に終了していますが、今後の公募に備えるためにも、全体の流れを把握しておくことが重要です。
支援対象者
第11次公募は、「専門家活用型」に特化しています。この枠の支援対象者は、事業承継やM&Aを検討している中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)です。
具体的には、事業を譲り渡す「売り手」側と、事業を譲り受ける「買い手」側の双方が対象となります。
補助対象となるのは、以下の通りM&A支援機関に登録された専門家に支払う経費です。
・仲介手数料
・ファイナンシャルアドバイザー(FA)費用
・デューデリジェンス(DD)費用
・セカンドオピニオン費用
これらの活動は、M&Aの成功に直結するため、本補助金は費用面での支援により大きな後押しとなります。
11次公募と過去のM&A補助金の違い
第11次公募における最大の変更点は、支援対象が実質的に「専門家活用型」に一本化されたことです。過去の公募では、M&A後の経営統合を支援する「PMI推進枠」や、廃業・再チャレンジを支援する枠も存在しましたが、最新の公募ではM&Aプロセスそのものにかかる専門家費用に焦点が当てられています。
また、「事業承継補助金」という類似の制度がありますが、こちらは事業譲渡に伴う設備投資や販路開拓費用なども対象に含む場合があり、より広い範囲をカバーしています。
一方で、本補助金はM&Aの「実行段階」における専門家支援に特化している点が大きな特徴です。自社の目的がM&Aの実行支援にあるのか、事業承継後の経営革新にあるのかによって、適切な補助金を選択する必要があります。



事業承継・M&A補助金の4つの申請枠|補助金・補助上限・対象経費
事業承継・M&A補助金には、これまで複数の申請枠が設けられてきました。第11次公募では「専門家活用型」が中心となりますが、制度全体を理解するため、過去に実施された申請枠もあわせて解説します。
補助対象や上限額は枠ごとに異なるため、自社に合った支援策を見極めることが大切です。
① 事業承継促進枠
(※現在は公募されていません)
事業承継促進枠は、親族内承継や従業員承継を対象とした枠でした。
後継者が事業を継ぐ際に、経営計画の策定や研修などにかかる専門家費用が補助対象でした。事業承継を円滑に進めるための初期段階の取り組みを支援する目的がありました。
② 専門家活用枠
専門家活用枠は、第三者承継、すなわちM&Aを支援するための中心的な枠です。
売り手・買い手双方の中小企業を対象に、M&Aにかかる専門家費用を補助します。
| 項目 | 内容 |
| 補助額 | 50万円 ~ 800万円(買い手・売り手支援型共通) |
| 補助率 | 1/2または2/3 ※以下のいずれかの条件を満たす場合は2/3になる ①物価高の影響等により、営業利益率が低下している ②直近決算期の営業利益または経常利益が赤字 |
| 主な対象経費 | ・仲介手数料 ・FA費用 ・デューデリジェンス費用 ・企業価値評価費用 ・セカンドオピニオン費用 など |
| 対象者 | 事業譲渡・譲受を検討する中小企業・小規模事業者 |
| 注意点 | 補助金額が50万円未満の場合は補助対象外となります (補助率により必要経費は75万〜100万円以上) |
③ PMI推進枠
(※現在は公募されていません)
PMI(Post Merger Integration)推進枠は、M&A成立後の経営統合プロセスを支援する枠でした。
買い手企業が、売り手企業の従業員との円滑なコミュニケーションを図るための研修費用や、新たなITシステムを導入する際のコンサルティング費用などが対象でした。
M&A後の効果を最大化する重要なフェーズを支援する目的がありました。
④ 廃業・再チャレンジ枠
(※現在は公募されていません)
この枠は、事業承継やM&Aが成立せず、やむなく廃業を選択する事業者や、廃業後に新たな事業に挑戦する事業者を支援するものでした。
廃業手続きにかかる専門家への相談費用や、在庫処分費や原状回復費用などが補助対象でした。円滑な事業の退出と、経営者の再起を後押しするセーフティネットとしての役割を担っていました。

事業承継・M&A補助金の申請方法・手続きの流れ
事業承継・M&A補助金の申請には、準備から交付後の報告まで、いくつかのステップを踏む必要があります。br> すべてオンラインで完結するため、手続きの流れを理解し、計画的に進めることが採択へのポイントです。
ここでは、申請手続きの全体像を5つのステップに分けて具体的に解説します。
STEP1:申請要項の確認と準備開始
最初に、中小企業庁や補助金事務局の公式サイトで最新の「公募要領」を熟読し、自社が補助対象の要件を満たしているかを確認します。
申請は政府の電子申請システム「Jグランツ」から行うため、事前に「GビズIDプライム」アカウントの取得が必要です。
このIDは発行に数週間かかる場合があるため、公募開始前から早めに申請しておきましょう。あわせて、M&Aの基本的な方向性や事業計画の骨子も準備しておきます。
STEP2:事業計画書など必要書類の作成
次に、申請に必要な書類を準備します。申請の中心書類は「事業計画書」で、M&Aの目的や期待される効果、事業の成長戦略などを明確に記載します。
審査では、計画の妥当性や実現可能性が厳しく評価されます。
その他、M&A支援専門家との契約書や見積書、決算書などの財務諸表、会社の登記事項証明書など、公募要領で指定された書類を漏れなく揃えます。書類に不備があると審査の対象外となるため、慎重に確認しましょう。
STEP3:補助金の申請書類を提出
すべての必要書類が準備できたら、「Jグランツ」にログインし、画面の指示に従って申請情報を入力し、作成した書類をアップロードします。
申請期間の締切日時を厳守してください。締切を過ぎるといかなる理由でも受け付けられません。
申請後は、事務局からの問い合わせに備え、提出した書類の控えを必ず保管しておきましょう。
STEP4:審査結果の通知と採択決定
申請締切後、事務局による審査が行われ、採択・不採択の結果がJグランツを通じて通知されます。審査には通常1〜2ヶ月ほどかかります。
採択が決定すると、「交付決定通知書」が発行されます。ここで重要なのは、交付決定日より前に契約・発注した経費は補助対象外となる点です。
必ず交付決定を受けてから、専門家との契約や業務の着手(デューデリジェンスの開始など)を進めてください。
STEP5:補助金の交付
補助事業の期間内にM&Aプロセスを完了させ、専門家への支払いを終えた後、事務局に「実績報告書」を提出します。
この報告書には、契約書や請求書、振込明細など、経費の支払いを証明するための書類(契約書や領収書など)の添付が必要です。
事務局が実績報告書の内容を検査し、補助金額が最終的に確定した後、指定した銀行口座に補助金が振り込まれます。これにて一連の手続きは完了です。
事業承継・M&A補助金の申請に役立つ専門家・支援機関
本補助金の申請を円滑に進め、採択の可能性を高めるためには、各分野の専門家や支援機関のサポートが非常に有効です。
ここでは、それぞれの専門家がM&A補助金の申請プロセスにおいてどのような役割を果たし、どのようなメリットをもたらすのかを具体的に解説します。
自社の状況に合わせて、最適なパートナーを見つけましょう。
① M&A支援業者|案件の紹介と条件調整
M&A仲介会社やファイナンシャルアドバイザー(FA)は、M&A実務のプロフェッショナルです。
補助金の対象となるためには、依頼先のM&A支援業者が「M&A支援機関登録制度」に登録されている必要があります。
登録された専門家は、自社の希望条件に合った買い手・売り手候補を探し出し、マッチングを支援します。
また、客観的な企業価値評価(バリュエーション)を行い、交渉をサポートします。補助金の対象となる仲介手数料やFA費用の見積書作成はもちろん、契約書作成まで一貫して支援してくれるため、M&Aプロセス全体を安心して任せることができます。
【費用の目安】
・相談料: 無料の場合が多い
・着手金: 0円~200万円程度
・中間金: 成功報酬の10%~20%程度、または100万円~200万円程度の固定額
・成功報酬: レーマン方式(取引価額5億円以下の部分に5%など)で算出。最低報酬額(数百万円~)が設定されている場合が多い。
② 中小企業診断士|事業計画の策定支援
中小企業診断士は、経営に関する国家資格を持つ専門家です。
補助金申請の核となる事業計画書の作成において、強力なパートナーとなります。
企業の現状を客観的に分析して課題を抽出し、M&Aによってどのようなシナジーが生まれ、事業がどう成長するのか、説得力のあるストーリーを構築します。採択審査で評価される「経営革新計画」の策定支援も可能であり、補助金の採択率向上に大きく貢献します。
【費用の目安】
・相談料: 1万円~3万円/時間程度
・事業計画書作成支援: 30万円~100万円程度(事業規模や内容による)
・顧問契約: 5万円~/月程度
③ 税理士|財務諸表の作成支援
税理士は、税務と会計の専門家です。
補助金申請には、過去数年分の決算書や試算表といった正確な財務諸表の提出が求められます。
顧問税理士に依頼すれば、必要な書類を円滑に準備できます。また、M&Aに伴う税務リスクの洗い出しや、最適なスキーム(株式譲渡、事業譲渡など)の検討、補助対象経費の根拠となる資料作成など、財務・税務面から申請を強力にバックアップしてくれます。
【費用の目安】
・財務諸表作成支援:顧問契約に含まれる場合が多い。別途依頼の場合は5万円~
・財務デューデリジェンス: 50万円~数百万円程度(調査範囲による)
・税務スキーム相談: 10万円~
④ 商工会議所|制度案内と申請相談
全国各地にある商工会議所や商工会は、地域の中小企業にとって最も身近な相談窓口です。事業承継・M&A補助金の制度概要や最新の公募情報を提供してくれるほか、申請書の書き方に関する基本的な相談に応じてくれます。
地域のネットワークを活かして、地元の専門家(中小企業診断士や税理士)を紹介してもらえたり、場合によっては地元企業とのマッチングを支援してくれたりすることもあります。
【費用の目安】
・相談料:会員は無料の場合が多い。専門家派遣なども安価または無料で利用できる場合がある。
⑤ 認定支援機関|補助金全体の支援対応
認定経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上あるとして、国から認定を受けた機関です。中小企業診断士、税理士、金融機関などが認定を受けています。
補助金申請全体のプロセスを熟知しており、事業計画の策定から申請書類の作成・チェック、採択後の実績報告まで、トータルでサポートを提供します。
【費用の目安】
・補助金申請サポート:支援内容によるが、着手金(数万円~)+成功報酬(補助金額の10%~20%程度)という料金体系が多い。事業計画の策定から関わる場合は、数十万円以上になることもある。


コストを抑えるなら、M&Aプラットフォームで相手を探す選択肢も
M&Aにかかるコストを抑えたい場合は、M&Aプラットフォームの活用が有効な選択肢です。
仲介会社を利用する場合、成功報酬として取引価額の数%(例:5億円以下の部分に5%)、最低でも数百万円以上の費用が必要になります。
一方、国内最大級のM&Aプラットフォーム「トランビ」などでは、売り手は無料で案件を登録でき、買い手も月額料金のみで交渉を始められます。仲介会社を介さないため、高額な成功報酬がかかりません。
例えば、取引価額1億円のM&Aの場合、仲介会社では500万円の成功報酬がかかるケースでも、プラットフォームならその費用を数万円~数十万円程度まで大幅に削減できます。複数の候補と直接やりとしりながら方向性を決め、必要な専門家だけを依頼できる柔軟な進め方が可能です。



事業承継・M&A補助金の活用事例

実際に補助金はどのように活用され、どのような成果につながっているのでしょうか。ここでは、Web上で公開されている具体的な企業の活用事例を5つ紹介します。
自社の状況と照らし合わせながら、活用のイメージを膨らませてみてください。
事例①:電子部品・デバイス・電子回路製造業(神奈川県)|技術力の高い会社の存続
課題:
長年にわたり健全な経営を続け、日本の高度な電子部品製造に貢献してきた企業でしたが、社長の病気により会社の存続が困難となりました。地域や取引先、雇用への影響を考え技術力のある会社の存続が強く求められました。
補助金の活用と成果:
株式譲渡による会社の存続を図るため、事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用×売り手支援型)の委託費として補助金が活用されました。これにより、技術力の高い会社の継続が実現し、地域経済、取引先、社員の雇用が維持されました。
出典:中小企業庁「令和5年度補正予算 事業承継・引継ぎ補助金 事例集」
事例②:飲食サービス業(愛知県)|グループ化による収益性と生産性の向上
課題:
工事現場で働く方々への食事提供を通じて事業を拡大してきたものの、遠いエリアの案件では収益性が低下することが課題でした。また、食材の一括購買や物流コストの削減、生産性と収益性の向上が課題でした。
補助金の活用と成果:
飲料卸売業を核とする企業グループへの事業引継ぎを通じて、異なる地域に強みを持つ関連企業との連携を図るため、事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用×売り手支援型)の委託費として補助金が活用されました。この補助金活用により、各社が強みを持つエリアに経営資源を集中させることが可能となり、生産性と収益性の向上、食材の一括購買によるコスト削減、物流コストの削減といった大きなシナジー効果が創出されました。
出典:中小企業庁「令和5年度補正予算 事業承継・引継ぎ補助金 事例集」
事例③:製造業(岡山県)|木材事業の拡大とコスト競争力強化
課題:
木材事業のスケール拡大とコスト競争力の強化を図るため、産業廃棄物収集運搬・処分業の承継が必要とされました。具体的には、産業廃棄物の取り扱い種類の拡大、競争力が弱いエリアの強化、そして自社収集運搬によるコスト低減の実現が課題でした。
補助金の活用と成果:
産業廃棄物収集運搬・処分業を承継し、木材事業のスケール拡大とコスト競争力強化を目指すため、事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用×買い手支援型)の委託費として補助金が活用されました。この承継により、地域の雇用維持や事業におけるシナジー効果の創出が図られ、当初の目的が達成されました。
出典:中小企業庁「令和5年度補正予算 事業承継・引継ぎ補助金 事例集」
事例④:スポーツ用品小売業(静岡県)|学校販売事業への進出と地域貢献
課題:
既存の小売事業と親和性の高い小中高生向けの学校販売事業への進出と新たなマーケット開拓が求められていました。同時に、地方で在庫を抱えるスポーツショップの救済や後継者不足の解消を通じて、学校スポーツのインフラを守ることも目的とされていました。
補助金の活用と成果:
学校販売事業への参入や地方店舗の支援、後継者不在の課題解消を目的に、事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用×買い手支援型)の委託費として補助金が活用されました。これにより、承継元の顧客への当社の認知度向上が期待され、スポーツ用品を通じた学校スポーツのインフラ維持に貢献できると考えられています。
出典:中小企業庁「令和5年度補正予算 事業承継・引継ぎ補助金 事例集」
事例⑤:建設業(新潟県)|地域技術の継承と雇用の維持
課題:
永続的な高品質サービスの提供のため、マルチな総合設備工事会社を目指すにあたり、譲渡先会社が持つ工事分野のノウハウや人材技術が重要と判断されました。また、地域経済における技術継承や雇用継続の必要性とその使命感も目的とされました。補助金の活用と成果:
技術継承と雇用継続を目的とした事業引継ぎのため、事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用×買い手支援型)の委託費として補助金が活用されました。これにより、熟練社員の雇用や取引先との関係も保たれ、企業の安定と成長が見込まれます。
出典:中小企業庁「令和5年度補正予算 事業承継・引継ぎ補助金 事例集」
2025年以降の事業承継・M&A補助金の展望

日本社会全体で中小企業の人手不足や後継者問題はますます深刻化しており、事業承継・M&Aを促進する補助金の重要性は今後さらに高まっていくと予想されます。
ここでは、今後の制度改正の動向と、補助金の活用を検討する経営者や担当者が今から備えておくべきことについて考察します。
制度改正・今後のトレンド
事業承継・M&A補助金は、費用補助にとどまらず、円滑な事業引継ぎと成長を支援する戦略的ツールへ進化していくと考えられます。
近年の「中小企業活性化パッケージ」や中小企業政策審議会での議論を踏まえると、特に「事業承継の促進」という文脈では、以下の4つのトレンドが今後の制度改正の核になると考えられます。
- 「プッシュ型支援」と「磨き上げ」の連携強化:
これまでの「待ち」の姿勢から、支援機関が潜在的な後継者不在企業へ積極的に働きかける「プッシュ型支援」への転換が、公式な方針として示されています。今後は、プッシュ型支援で見つかった企業が「磨き上げ」に取り組む際の費用(例:DX導入や事業の見直し)への補助が強化される可能性があります。これは、承継の「入口」から「準備段階」までを一体的に支援する流れを加速させるものです。 - 経営者保証解除に向けた支援の具体化:
事業承継の大きな障壁である経営者保証問題。政府は「経営者保証改革プログラム」を推進しており、事業承継時の保証解除を円滑に進めるための動きが活発化しています。これにより、保証解除に必要な資料作成や財務整理の費用が補助対象となる可能性があります。 - 多様な承継形態への対応と担い手の育成:
第三者へのM&Aだけでなく、親族内承継や従業員承継(EBO)も重要な選択肢です。中小企業庁の「事業承継ガイドライン」でも多様な承継の検討が推奨されており、今後はこれらの承継形態に特化した支援メニュー(例:後継者教育プログラム費用、従業員持株会の設立支援費用など)が拡充されることが考えられます。また、承継を支援する側の専門家(M&A支援機関)の質の向上と、担い手となる人材育成に関する取り組みへの支援も強化されるでしょう。 - 地域金融機関・支援機関との連携深化:
中小企業の事業承継は、地域経済の存続に直結する課題です。そのため、地域の金融機関や商工会議所、事業承継・引継ぎ支援センターが連携し、地域ぐるみで承継を支援する体制の構築が急がれています。今後は、地域の支援機関による企業発掘やマッチングなどの活動が、重点支援の対象になると見込まれます。
これらの動向は、本補助金が単にM&Aの件数を増やすだけでなく、一社一社の事業承継の「質」を高め、地域社会の活力を維持するための重要な政策ツールとして進化していくことを示唆しています。
中小企業経営者・担当者が押さえるべきポイント
経営者やM&A担当者が今すぐ取り組むべきことは、第一に「情報収集の習慣化」です。中小企業庁や補助金事務局のウェブサイトを定期的に確認し、常に最新の公募情報をキャッチできる体制を整えましょう。
第二に、「事前の準備」です。補助金の電子申請に必須の「GビズIDプライム」は、早めに取得しておくに越したことはありません。
また、補助金の活用を前提に、自社の強みや課題、目的を整理しておけば、申請時に慌てずに対応できます。
事業承継・M&A補助金に関するよくある質問
最後に、本補助金に関して多く寄せられる代表的な質問とその回答をQ&A形式でまとめました。
申請を具体的に検討する上での疑問点や不安を解消するためにお役立てください。
専門家を使わないM&Aも補助対象になる?
専門家を使わないM&Aは補助対象になりません。この補助金は、M&A支援機関登録制度に登録された専門家の活用を支援し、その手数料や報酬の一部を補助する制度です。
したがって、登録専門家を介さずに当事者間のみで進めるM&Aは、補助の対象外となります。補助金を利用するには、M&A支援機関登録制度に登録された専門家との契約が必要です。
M&A後のPMI・統合フェーズも補助される?
第11次公募の「専門家活用型」では、M&A後のPMI(経営統合)フェーズを直接の補助対象としていません。補助対象は、あくまでM&Aの成立に向けたプロセスで発生する専門家費用です。
しかし、M&Aの契約にPMIに関するコンサルティングが含まれており、それが専門家費用として一体的に支払われる場合など、条件によっては補助対象と認められる場合もあります。
このような場合は、申請前に必ず補助金事務局に問い合わせて、対象範囲を確認することが重要です。
申請の採択率・傾向、再申請はできる?
採択率は公募回や申請件数によって変動するため一概には言えませんが、一般的に数十パーセント程度とされています。審査では、事業計画の具体性、M&Aの必要性、地域経済への貢献度、計画の実現可能性などが総合的に評価される傾向にあります。
費用面だけでなく、M&Aによる成長や地域への影響を具体的に説明することが重要です。
万が一不採択となった場合でも、事業計画を見直し、要件を満たしていれば次回の公募で再申請することは可能です。
まとめ
本記事では、令和6年度補正予算で実施された2025年の事業承継・M&A補助金(専門家活用型)について、その概要から申請方法、注意点までを網羅的に解説しました。
現在の補助金制度は、M&Aプロセスにおける専門家活用を支援する「専門家活用型」が中心です。FAや仲介業者への手数料、デューデリジェンス費用などが補助対象となり、M&A実行の金銭的なハードルを大きく下げてくれます。
申請を成功させるためには、まず電子申請に必要な「GビズIDプライム」を早期に取得し、公募要領を熟読することが第一歩です。
その上で、M&Aの目的や効果を明確にした事業計画書を立て、登録専門家と連携することが大切です。
後継者不在や事業成長といった経営課題の解決策としてM&Aを検討している経営者・担当者の方は、この補助金制度を有効活用し、企業の未来を切り拓くための一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。





