
事業承継・M&Aエキスパートとは?取得方法・難易度・実務活用まで徹底解説
自身のM&Aに関する知識レベルの客観的な証明や交渉や実務を有利に進めていくための解決策が「事業承継・M&Aエキスパート」です。資格取得までの具体的な道のりを明確にし、ビジネスを加速させるための情報収集にお役立てください。
M&Aや事業承継の成功には、専門知識が欠かせないと感じる経営者や担当者も多いのではないでしょうか。「自身のM&Aに関する知識レベルを客観的に証明したい」「体系的なスキルを身につけて、交渉や実務を有利に進めたい」といった課題感をお持ちかもしれません。
その解決策が「事業承継・M&Aエキスパート」です。この資格は、M&Aや事業承継に関する専門知識を体系的に有していることを証明するもので、実務能力の向上と信頼性の証明に直結します。
本記事では、事業承継・M&Aエキスパートの概要から、取得のメリット、具体的な試験内容、効果的な勉強方法、さらには資格取得後のキャリア活用例まで、わかりやすく解説します。
この記事を最後まで読めば、資格取得までの具体的な道のりが明確になり、M&Aの専門家としてキャリアアップするための確かな一歩を踏み出せるはずです。ぜひ、あなたのビジネスを加速させるための情報収集にお役立てください。


事業承継・M&Aエキスパートの概要

事業承継・M&Aエキスパートは、M&Aや事業承継に関する専門知識を体系的に習得し、その能力を客観的に証明するための重要な指標です。
本章では、この資格がどのような目的で創設され、どのような試験制度で運営されているのか、その全体像を明らかにします。
また、資格のレベルや難易度についても触れ、取得を検討する上での基礎知識を詳しく解説します。
事業承継・M&Aエキスパートの概要と目的
事業承継・M&Aエキスパートは、「事業承継・M&A 資格認定・支援制度」の一つであり、M&Aや事業承継の実務に必要な知識を体系的に習得することを目的とした資格です。特に中小企業のM&Aや事業承継の場面で活躍できる人材の育成を目指しています。
資格を取得すれば、企業価値評価や契約、PMIなどM&Aの全体像を理解していることを示せます。経営者自身が取得すれば、自社のM&A戦略を円滑に進めることができ、企業の担当者が取得すれば、専門家として社内外で信頼される専門知識を備えることができます。
事業承継・M&A 資格認定・支援制度と運営団体
事業承継・M&A 資格認定・支援制度は、株式会社日本M&Aセンターおよび株式会社きんざいが共同で制度を創設し、一般社団法人金融財政事情研究会が試験の実施・運営から資格の認定までを行っています。
この「事業承継・M&A 資格認定・支援制度」は、知識レベルに応じて4段階の資格に分かれています。具体的には、「事業承継・M&Aベーシック」「事業承継・M&Aエキスパート(スタンダード)」「事業承継シニアエキスパート」「M&Aシニアエキスパート」の順にレベルが上がっていきます。
一般的に「事業承継・M&Aエキスパート」と呼ばれる本資格は、この中の「スタンダード」レベルに位置づけられており、M&Aや事業承継の全体像を学びたい初学者や、実務の基本を身につけたい人向けの資格です。
一方、上位資格である「事業承継シニアエキスパート」や「M&Aシニアエキスパート」は、複雑な案件に対応するコンサルタントや金融機関を対象としています。
取得者数・難易度の目安
事業承継・M&Aエキスパートは、2020年9月時点で有資格者数が約3万人と発表されており、M&A・事業承継分野における関心の高さがうかがえます。
合格率は公式には発表されていませんが、一般的には「事業承継・M&Aエキスパート」の難易度は標準レベルとされています。公式テキストと問題集を使って学習すれば、独学でも合格を目指せます。ただし、法務や税務、会計といった専門分野に関する知識が問われるため、実務経験のない方にとっては、計画的な学習が不可欠です。
M&Aや事業承継の知識を体系的に証明する第一歩として、多くのビジネスパーソンにとって価値のある資格と言えるでしょう。


事業承継・M&Aエキスパートの試験概要

事業承継・M&Aエキスパート試験の合格を目指す上で、試験内容を事前に把握しておくことが重要です。
ここでは、試験時間や形式、合格ラインなど、受験前に必ず確認しておきたい試験の全体像を具体的に解説します。
試験形式・試験時間
試験は、全国のテストセンターに設置されたコンピュータを使用して解答するCBT(Computer Based Testing)形式で実施されます。CBT方式のため、日時や場所を自分の都合に合わせて選べます。
試験時間は120分間です。全問を時間内に解く必要があるため、時間配分を意識した対策が求められます。
出題数・合格基準
出題は、四答問題30問と、総合問題10題の計40問です。M&Aや事業承継に関する幅広い分野から出題され、体系的な知識が求められます。
合格ラインは100点中70点以上です。苦手分野を作らず、バランス良く学ぶことが合格への鍵です。
受験資格・受験料
この試験には、学歴や国籍、実務経験などの制限は一切ありません。M&Aや事業承継に関心のある方であれば、どなたでも受験することが可能です。
受験料は税込7,700円です(2025年7月現在)。最新情報は金融財政事情研究会の公式サイトで確認し、申し込み時に支払います。
事業承継・M&Aエキスパートを取得するメリット

事業承継・M&Aエキスパートの取得は、知識の証明だけでなく、実務やキャリアにも直接役立ちます。
専門知識を体系的に習得できるだけでなく、社内外での信頼性を高め、キャリアアップにもつながる有効な資格です。本章では、資格取得がもたらす3つの主要なメリットについて、詳しく掘り下げて解説します。
① M&Aや事業承継に関する専門知識を体系的に習得できる
最大のメリットは、M&Aや事業承継の知識を体系的に学べることです。M&Aの実務は、法務、税務、会計、労務、企業価値評価など、多岐にわたる専門分野の知識を必要とします。
独学では知識が断片的になりやすく、全体像や関連性を理解するが難しいこともあります。事業承継・M&Aエキスパートの学習過程を通じて、M&Aの初期検討段階から最終的な統合プロセスまでの一連の流れを、必要な知識を効率よく習得できます。
これにより、実務で直面する様々な課題に対して、理論に基づいた的確な判断を下すための土台が築かれます。
② 社内外での信頼性と専門性の証明に役立つ
事業承継・M&Aエキスパートは、あなたの専門性を客観的に証明するツールになります。M&Aの交渉相手や金融機関、提携先の専門家など、社外のステークホルダーに対して、あなたが一定水準以上の知識を有していることを示すことができます。
これにより、円滑なコミュニケーションと信頼関係の構築が期待できます。また、社内においても、経営層や他部署のメンバーからM&Aプロジェクトのキーパーソンとして認識され、意見の説得力が増すでしょう。
専門性が可視化されることで、プロジェクトの推進力向上にもつながり、より重要な役割を任される機会も増えるはずです。
③ キャリア・ビジネス展開における優位性の向上
資格取得は、自身のキャリア形成における強みになります。企業内でM&Aや事業承継を推進する部署への異動や、プロジェクトリーダーへの抜擢など、より専門性の高い業務に携わるチャンスが広がります。
また、転職市場においても、M&Aに関する専門知識を持つ人材の需要は高く、特に金融機関やコンサル会社、経営企画部門などへの転職にも有利です。資格という客観的な証明があることで、自身のスキルを客観的に示す手段となり、より良い条件でのキャリアアップが期待できるでしょう。

事業承継・M&Aエキスパートの試験内容と出題範囲
事業承継・M&Aエキスパート試験の合格には、出題内容を正確に把握し、効率よく対策することが重要です。
試験は大きく5つの分野から構成されており、事業承継とM&A、税制・法制・会計の基礎が中心です。本章では、各分野の具体的な出題範囲と学習のポイントを解説します。
事業承継関連税制等
この分野では、事業承継に伴って発生する税務に関する知識が問われます。具体的には、相続税や贈与税の計算方法、納税猶予制度といった事業承承継税制の特例措置などが中心です。
非上場株式の納税猶予制度は、中小企業の円滑な事業承継を支える重要な制度であり、その要件や手続きの流れを正確に理解しておく必要があります。計算問題も出題される可能性があるため、暗記だけでなく、応用力を身につけることが合格への鍵となります。
事業承継関連法制等
事業承継関連法制の分野では、主に会社法や民法(特に相続法)に関する知識が問われます。株式の譲渡や相続、遺言、遺産分割協議、遺留分など、親族内承継や従業員承継において法的に問題となるポイントが中心です。
また、経営承継円滑化法に基づく支援措置についても理解が求められます。法律の細かな知識だけでなく、実務での使われ方も意識して学習しましょう。種類株式の活用法など、具体的な対策手法と関連付けて知識を整理すると良いでしょう。
M&A基礎知識・関連会計
この分野では、M&Aの基本的なプロセスや手法、そして企業価値評価(バリュエーション)に関する会計知識が問われます。M&Aの各スキーム(株式譲渡、合併など)の特徴やメリット・デメリットを正しく理解することが基本です。
さらに、DCF法、純資産法、類似会社比較法などの主要な企業価値評価方法の計算方法や考え方を習得する必要があります。財務三表(B/S、P/L、C/F)の基本も重要で、評価の土台となるため、しっかりと復習しましょう。
M&A関連法制等
M&A関連法制では、M&Aプロセスを規律する法的な枠組みに関する知識が問われます。中心となるのは会社法で、株式譲渡や組織再編行為(合併、会社分割、株式交換等)に関する手続きや規制について深く理解しておく必要があります。
その他、金融商品取引法における情報開示(ディスクロージャー)規制や、独占禁止法における企業結合審査など、関連する法律の知識も求められます。法務デューデリジェンスのチェック項目とも関連があるため、実務をイメージしながら学習を進めると理解が深まるでしょう。
総合問題
総合問題では、これまでにあげた4つの分野(事業承継税制・法制、M&A基礎・会計・法制)の知識を横断的に活用して、具体的なケーススタディに取り組む形式の問題が出題されます。
ある企業の事業承継やM&Aのシナリオが提示され、最適なスキームの提案や、その際に生じる法務・税務・会計上の課題を分析・解決する能力が試されます。各分野を理解するだけではなく、統合して答えを導く力が問われます。過去問や問題集を活用し、実践的な演習を繰り返すことが最も効果的な対策となります。



事業承継・M&Aエキスパートの効果的な勉強方法
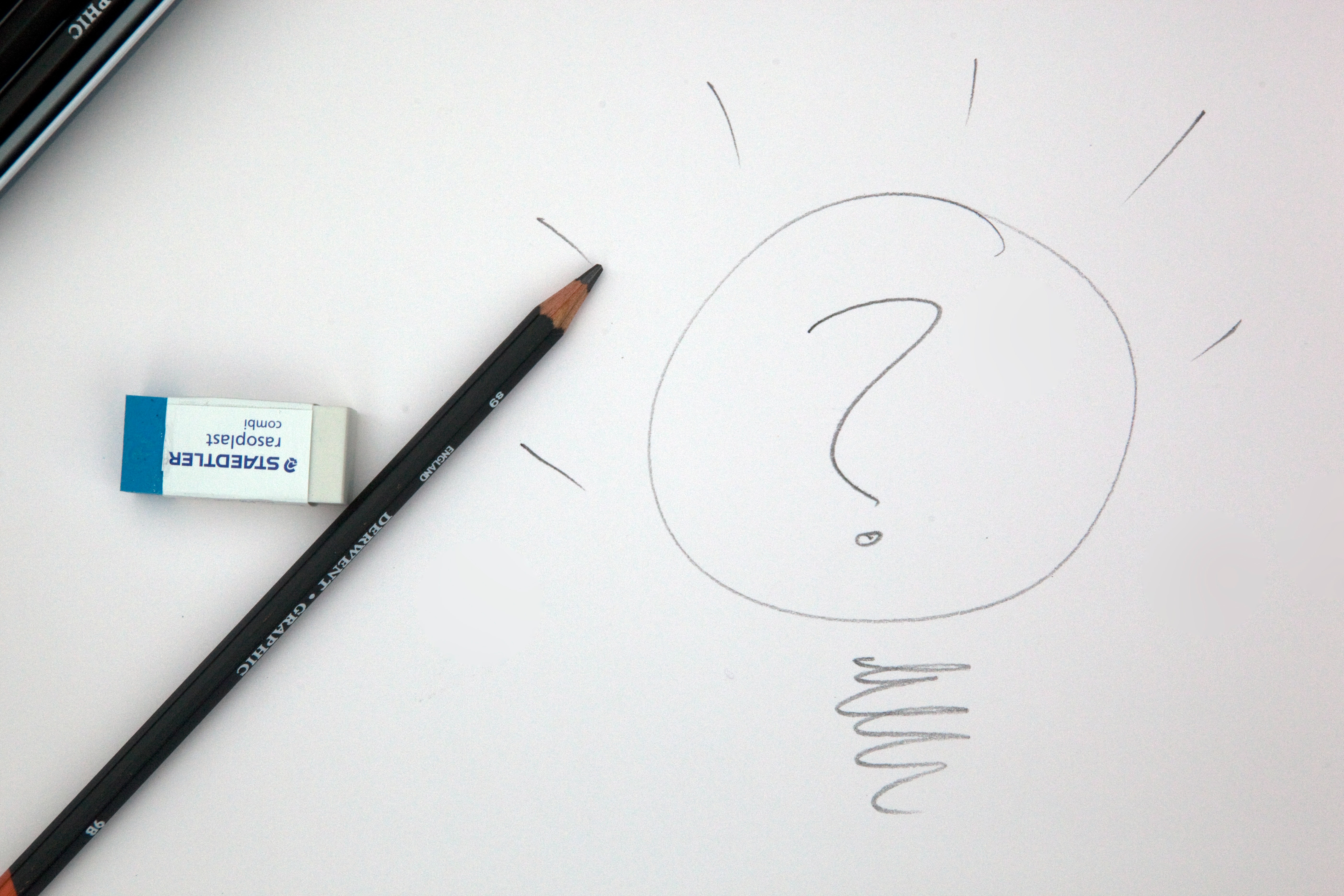
事業承継・M&Aエキスパートの合格には、無計画に勉強するのではなく、効率的な学習計画を立てることが大切です。
自分に合った学習スタイルを見つけ、適切な教材を使えば、短い時間でも効率よく実力を伸ばせます。本章では、具体的な勉強スケジュールの立て方から、教材の選び方、独学と講座の比較まで、合格への最短ルートを解説します。
合格に向けた効率的な勉強スケジュールの立て方
事業承継・M&Aエキスパートの合格に必要な勉強時間の目安は、30~90時間程度とされています(中級者の場合)。ただし、これは法務や会計の基礎知識がある場合の目安であり、初学者の場合はもう少し余裕を持ったスケジュールを組むと良いでしょう。
例えば、1日1時間なら、1~2ヶ月を目安に計画すると良いでしょう。
①テキストで全体像を掴む、②分野別の学習、③過問題演習の3ステップがおすすめです。自分のライフスタイルに合わせて無理のない計画を立て、継続することが何よりも大切です。
テキストや参考書・過去問の選び方
事業承継・M&Aエキスパート試験の学習において、最も重要な教材は、試験の運営団体である金融財政事情研究会(きんざい)の公式テキストと問題解説集です。試験問題はこの公式テキストの内容に準拠して作成されるため、まずは公式教材をしっかり読み込み、理解することが合格の基本となります。
市販の参考書は、図解が多くて分かりやすいものや、特定の分野を深掘りしているものなど特色があります。公式テキストで理解しにくい部分を補う補助的な教材として活用するのが良いでしょう。過去問は非公開ですが、問題解説集が実践演習に最適です。繰り返し解き、間違えた箇所はテキストに戻って復習するサイクルを確立しましょう。
独学と通信講座・対策講座の比較と選び方のコツ
学習方法は「独学」か「通信講座・対策講座」の二択です。独学の最大のメリットは、費用を抑えられる点と、自分のペースで学習を進められる点です。公式テキストが充実しているため、自己管理ができる方であれば独学での合格も十分に可能です。
一方、通信講座や対策講座は、専門の講師による分かりやすい解説や、最新の試験傾向を踏まえたカリキュラムが魅力です。「一人だと学習のやる気が続かない」「短期間で効率的に合格したい」という方には適しています。費用はかかりますが、質問対応などのサポートもあり、つまずきにくいのが特徴です。自身の知識レベルや予算、学習に割ける時間を考慮して、最適な方法を選択しましょう。
事業承継・M&Aエキスパートの取得までの流れ

事業承継・M&Aエキスパートの取得は、いくつかのステップに分かれています。申し込みから受験、そして認定証取得までの流れを理解しておくことで、スムーズに対応できます。
本章では、資格取得までの3つのステップを順に解説します。
Step1. 試験の申し込み
まずは、試験運営団体である金融財政事情研究会のウェブサイトから受験申し込みを行います。氏名、住所などの個人情報を登録し、受験料を支払います。この際、登録する氏名は、本人確認書類と完全に一致させる必要があります。
申し込みが完了したら、CBT方式のテストセンターから空き状況を確認し、自分の都合の良い日時と会場を予約します。年間を通じて随時受験が可能なので、学習計画に合わせて柔軟に日程を組むことができます。
Step2. CBTテストセンターでの受験
試験当日は、予約したテストセンターへ向かいます。受付では、運転免許証やマイナンバーカードといった顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。忘れると受験できないため、事前に必ず準備しておきましょう。
試験はコンピュータ上で行われ、電卓や筆記用具は会場に備え付けのものを使用します。試験が終了すると、結果が画面に即時表示され、スコアレポートを受け取ることができます。
Step3. 合格後の手続きと認定登録
試験に合格した後は、資格認定団体である金融財政事情研究会のウェブサイトで認定登録の手続きを行います。この手続きはオンラインで完結し、認定料の支払いは不要で、合格後すぐに資格認定されます。
登録後、認定証はデータ形式でダウンロードが可能になるほか、希望すればカード型認定証を郵送の郵便受付も可能です。これで、M&Aエキスパートとしての第一歩が完了します。



事業承継・M&Aエキスパートの活用例と取得後のキャリアへの影響

事業承継・M&Aエキスパートは、取得そのものがゴールではありません。その知識と信頼性をいかに実務やキャリアに活かしていくかが重要です。
企業内でプロジェクトを推進する立場であれ、専門家としてクライアントに価値を提供する立場であれ、この資格はキャリアの選択肢を広げるきっかけになります。本章では、具体的な活用シーンとキャリアへの好影響について解説します。
企業内における事業承継・M&Aエキスパート資格の活用例
企業内でこの資格を持つ人材は、M&Aや事業承継プロジェクトにおいて中心的な役割を担うことが期待されます。例えば、経営企画部や財務部に所属し、自社の成長戦略としてM&Aを検討する際の候補先リストアップ、初期交渉や資料収集の支援などを行うケースもあります。
また、後継者問題を抱える企業においては、事業承継プロジェクトのリーダーとして、現経営者や後継者候補と専門家との橋渡し役を務めることが期待されます。資格で得た体系的な知識があることで、弁護士や会計士といった外部の専門家とも対等に議論を進められ、自社にとって最適な意思決定を導くための推進力となるでしょう。
コンサルタントや士業が資格を活用する場面
弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士といった士業や、経営コンサルタントがこの資格を取得することで、自身の専門性にM&Aという付加価値を加えることができます。クライアントから事業承継やM&Aに関する相談を受けた際に、より具体的で踏み込んだアドバイスが可能になります。
税理士であれば、事業承継の相談に対して、税務とM&Aを両面から提案できます。
資格を保有していることが対外的な信頼性の証明となり、新規顧客の獲得や、より高付加価値なコンサルティング業務への展開に繋がるケースも少なくありません。

事業承継・M&Aエキスパートに関するよくある質問
事業承継・M&Aエキスパートの受験を検討するにあたり、多くの方が抱くであろう疑問や不安があります。
合格率や勉強時間といった具体的な数値から、資格のレベル感、学習方法まで、気になるポイントは様々です。本章では、これらのよくある質問に対して、Q&A形式で分かりやすく回答していきます。
事業承継・M&Aエキスパートの合格率は?
事業承継・M&Aエキスパートの合格率は、公式には発表されていません。
しかし、一般的には標準的な難易度とされており、公式テキストと問題集を中心にしっかりと対策すれば、十分に合格が可能な試験です。
合格までの試験勉強時間の目安は?
合格までの勉強時間の目安は「事業承継・M&Aエキスパート」の場合、30時間から90時間程度です。1日1〜2時間の学習を1ヶ月続ければ達成可能な目安です。初学者の場合は、これよりも多い50時間~90時間程度の学習時間を見込んでおくと、より安心して試験に臨めるでしょう。
もちろん、これはあくまで目安であり、個人の理解度や学習ペースによって調整が必要です。重要なのは、総勉強時間よりも、継続して学習する習慣をつけることです。CBT方式で随時受験できるため、自分の学習の進捗に合わせて受験日を決められるのが利点です。
焦らず、自分のペースで着実に知識を積み重ねていきましょう。
独学でも合格できる?
結論から言うと、独学での合格は十分に可能です。その最大の理由は、試験内容が公式テキストに準拠しており、学習範囲が明確であるためです。金融財政事情研究会(きんざい)から出版されている公式テキストと問題解説集を繰り返し学習することが、合格への王道ルートと言えます。
ただし、法務や会計の知識が全くない方や、一人では学習のモチベーションを維持するのが難しいと感じる方もいるでしょう。
そうした場合は、予備校などが提供する通信講座や対策講座の利用を検討するのも一つの有効な手段です。自分の特性や状況に合わせて、最適な学習スタイルを選択してください。
まとめ|事業承継・M&Aエキスパートを取得してキャリアアップを目指そう!
本記事では、事業承継・M&Aエキスパートの概要からメリット、試験内容、勉強法、そして取得後の活用例までを網羅的に解説しました。この資格は、複雑化するM&Aや事業承継の実務において、羅針盤となる体系的な知識を与えてくれます。
この資格取得で得られるのは、実務に役立つ統合的な専門知識と応用力です。それは、社内外での信頼性を高め、M&Aプロジェクトを成功に導く推進力となり、ひいてはあなた自身のキャリアを大きく飛躍させる強力な武器となるでしょう。
M&Aの専門家としての第一歩は、正しい情報を収集し、具体的な行動計画を立てることから始まります。本記事が、その一助となれば幸いです。まずは公式サイトで詳細を確認し、あなたのキャリアアップに向けた挑戦を始めてみてはいかがでしょうか。





