
事業価値はどう決まる?算出方法や企業価値・株主価値との違いを紹介
M&Aで事業の譲渡価格を決めるには、対象企業の『事業価値』を見極めることが重要です。事業価値は企業価値の一部であり、将来的にどれだけの収益を生み出せるかを示します。企業価値・株主価値との違いや、価値の算出方法を解説します。

会社の価値を知るための指標

M&Aで事業譲渡を行う際は、売り手の事業の価値を見極め、双方が納得できる譲渡価格を決めなければなりません。M&Aで『価値』という言葉が出てくる際は、何の価値を示しているのか明確にする必要があります。
事業価値・企業価値・株主価値は全て『会社の価値』を知るために重要な指標です。


事業価値
『事業価値』は『EV(エンタープライズバリュー)』とも呼ばれます。『事業がもたらす価値』であり、『事業で将来どれだけのキャッシュフローを生み出せるか』を金額ベースで示したものです。
事業価値には、のれん(営業権)・商標権・特許権などの『無形資産』も含まれます。一般的な企業において、事業価値は企業価値の大部分を占め、『企業価値=事業価値+非事業用資産』という方式が成り立ちます。
企業価値
事業価値は企業価値の一部です。企業価値は、企業が保有する資産や将来的に生み出されるキャッシュフローなどを基に、現時点での会社全体の経済価値を金額ベースで示したものです。企業価値は以下の式から求められます。
- 企業価値=事業価値+非事業用資産
非事業用資産とは、『フリーキャッシュフローの増加に直接寄与しない資産』です。明確な定義はありませんが、主に以下の資産が含まれます。
- 遊休資産
- 出資金
- 投資有価証券・有価証券
- 保険積立金
- 余剰資金
株主価値
株主価値は、企業価値のうち『株主に帰属する価値』であり、企業価値から負債価値を差し引いたものです。
- 株主価値=企業価値-有利子負債
負債価値には、有利子負債や他人資本、デットライクアイテムなどが含まれます。『デットライクアイテム』とは有利子負債に類似する項目で、未払賞与・ファイナンスリース債務・退職給付債務・役員退職慰労引当金・偶発債務などを指します。
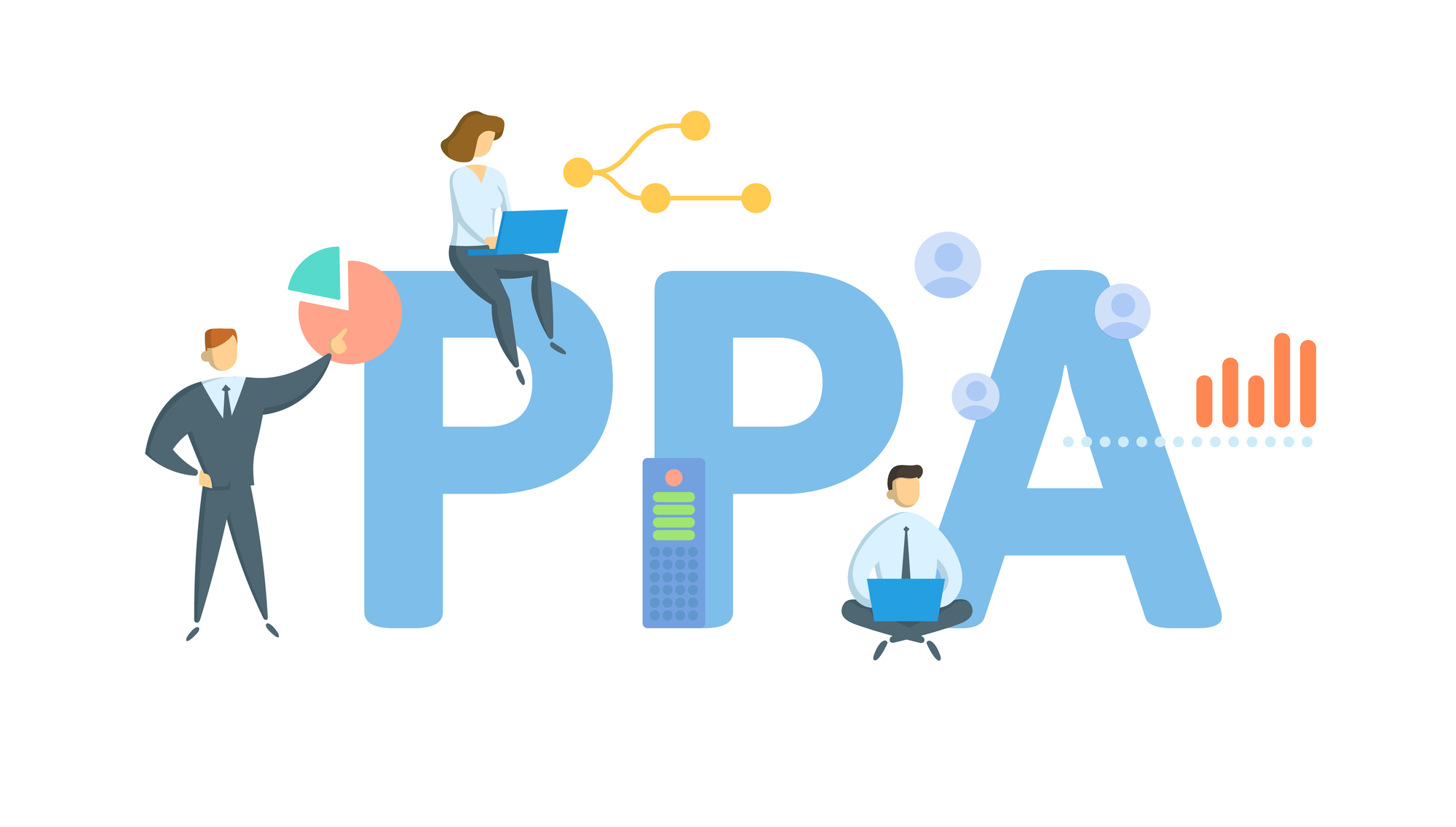
事業の譲渡価格の決まり方

M&Aで事業譲渡を行う際は、売り手と買い手の双方で『譲渡価格』を話し合います。どちらかが一方的に価格を提示するのではなく、交渉を重ねて最終的な価格が決まります。
売り手と買い手双方の合意で決まる
事業の譲渡価格は、売り手と買い手の交渉と合意によって決まります。最初に売り手が譲渡希望価格を提示して買い手候補を募り、買い手が現れた段階で交渉を重ねていくのが一般的な流れです。
譲渡金額に平均の相場はなく、会社の状況や業界の動向、交渉力などによって大きく左右されます。
事業譲渡の場合、譲渡価格は『譲渡する事業の価値』によって決まるのが一般的です。事業価値を算定するために、資産(流動資産・固定資産・無形資産)や事業で生じる負債を全て明らかにしなければなりません。
有形資産や負債だけでなく、営業権や商標権などの『無形資産・知的財産権』も加味し、企業の収益力を評価します。
条件交渉のタイミング
売り手と買い手の条件交渉はM&Aのどのタイミングで行われるのでしょうか?条件交渉は主に『基本合意書』と『事業譲渡契約』の際に行うと考えましょう。
- 経営者同士の会合
- 意向表明書の提出
- 基本合意書の締結
- デュー・デリジェンス(買収調査)の実施
- 事業譲渡契約の締結
最初に、双方の経営者同士で経営方針や譲渡価格などの基本的な事項を話し合います。買い手は『意向表明書』を提出してM&Aを進める意向を表明し、基本的な条件の交渉に進むのが通常です。
双方が合意に至った場合、『基本合意書』を締結し、デュー・デリジェンスに進みます。デュー・デリジェンスは買い手企業による売り手企業の買収調査で、事業価値や収益力、簿外債務(会計帳簿に記載されていない債務)の有無などを調査します。
デュー・デリジェンスの結果をもって『価格の最終交渉』を行い、合意に至った場合に事業譲渡契約を締結する流れです。


DCF法

M&Aにおいて、売り手企業の価値を評価するプロセスは『企業価値評価(バリュエーション)』と呼ばれます。評価方法に絶対的なものはなく、企業ごとに算出方法はさまざまです。大企業のM&Aで使われる『DCF法』を解説します。
大企業のM&Aで使われる
DCF法(Discounted Cash Flow)は、事業で将来的に得られるであろうキャッシュフローを基に事業価値を評価する『インカム・アプローチ』という方法です。
具体的には、事業計画や貸借対照表、損益計算書などから将来的な収益を推計し、資本コスト(資本調達のためにかかるコスト)で割り引いて現在価値を求めます。
将来の事業計画やのれんを反映した理論的な計算方法ではありますが、将来のキャッシュフローや割引率の精度によって、算出結果が大きく変わってしまうのがデメリットです。
正確かつ客観的な事業計画の存在が前提なので、中小企業よりも大企業で用いられる傾向があります。
算出方法
DCF法で事業価値を算出するには、いくつものステップを踏まなければなりません。ここでは、DCF法の計算式とキーワードの意味を解説します。
- 事業価値=将来のフリーキャッシュフロー(FCF)÷割引率(資本コスト)
割引率にある『資本コスト(WACC)』とは、事業活動に必要な資金調達にかかるコストのことです。他人資本(借入)と株式発行(自己資本)によるコストを加重平均して以下のように算出します。
- WACC(%)= 株主資本コスト×株主資本÷(有利子負債+株主資本)+負債コスト×(1-実効税率)×有利子負債÷(有利子負債+株主資本)


時価純資産法

将来的な収益を基に事業価値を算出するDCF法に対し、純資産を基に株式価値を評価する方法は『コスト・アプローチ』と呼ばれます。コスト・アプローチの代表的な手法である『時価純資産法』について説明します。
簿価純資産法との違い
コスト・アプローチ(純資産法)は純資産額から1株当たりの純資産額を算出する手法で、以下の二つに大別されます。
- 時価純資産法
- 簿価純資産法
簿価純資産法では、企業の資産・負債は『帳簿価格』に基づくのに対し、時価純資産法は『時価』に基づきます。
簿価純資産法は貸借対照表(BS)がそのまま活用できるため、算出に時間はかかりません。しかし、所有する不動産などに含み益・含み損がある場合、実態からかけ離れた価格が算定されてしまうのがデメリットです。
資産・負債を時価にする時価純資産法は、簿価純資産法のデメリットをカバーした算出方法といえるでしょう。
算出方法
時価純資産法では、貸借対照表(簿価)の資産・負債の全項目を時価に置き換えます。その後、資産から負債を差し引いた『時価純資産額』を株式価値として評価する流れです。
- 時価純資産額(=株式価値)=時価評価された資産-時価評価された負債
資産・負債の全項目を時価評価するのは容易ではありません。実際は、主要なものだけを時価で再評価するのが一般的です。含み損益があるものだけを時価評価する方法は『修正純資産法』と呼ばれています。
時価純資産法はこれまでの利益をベースに算出するため、将来的な収益が反映されません。成長過程のベンチャー企業には不向きといえます。
年倍法

年倍法は、コスト・アプローチの一種です。時価純資産法は企業の収益獲得能力が反映されませんが、これらの方法には『のれん(将来的な収益源となる無形資産)』が加わるため、企業の価値をより適正に評価できます。
のれんの価値も含まれる
年倍法には『のれんの価値』が含まれます。のれんとは、会社が所有する無形固定資産の一つです。以下のようなもので構成され、現金や不動産とは異なり数値化できないものの、将来の収益獲得には欠かせません。
- ノウハウ
- 特殊技術
- 立地条件
- 企業のブランド・地位
- 取引先・顧客
年倍法は『時価純資産+のれん代』で算出します。計算がわかりやすいことから、中小企業のM&Aで多く採用される傾向があります。
算出方法
年倍法は、営業利益に年数倍率(任意)をかけた値を時価純資産に加算する、簡便な方法です。年数(将来性)は、売り手と買い手の双方が納得できるものを設定する必要があります。
- 営業利益 × 年数倍率(任意)=のれん代
- のれん代+時価純資産

まとめ
M&Aでは、企業価値評価による算定を踏まえた上で、適正な譲渡価格を決定します。
売り手と買い手との間で『価値』に対する評価が分れると、価格交渉は難航します。交渉を円滑に進めるためにも、事業価値や譲渡価格の適切な算出方法を理解しておく必要があるでしょう。
事業価値の算出には専門的な知識と経験を要します。M&Aのアドバイザーや税理士と協力しながら進めましょう。
M&Aや事業売却・事業譲渡を検討中なら、まずはM&Aプラットフォーム「TRANBI」でどのような案件が世の中に集まっているのかを見てみましょう。常時2,500件以上の公開案件がご覧になれます。





