
M&Aの失敗事例。トラブルを回避するためのポイントを解説
日本におけるM&Aの成功率は、かなり低いとされています。M&Aの成功・失敗の定義は難しい面がありますが、想定していた効果が得られなければ、少なくとも成功したとはいえません。多くの失敗事例に触れ、トラブルやリスクを回避する方法を学びましょう。
「TRANBI」は、10万人以上のユーザーを抱える国内最大級のM&Aプラットフォームです。案件の掲載数は常時2,700件以上、未経験者によるM&A成約率は約75%に上ります。
無料の会員登録後は、M&A案件の最新状況が自由に閲覧できるほか、希望の事業を地域や業種、予算で検索可能です。気になる事業があれば、事業詳細をみて交渉をスタートできます。


M&Aで考えられる失敗パターン

M&Aによる企業買収には多くのメリットがありますが、必ずしも成功するわけではありません。常に失敗のリスクをはらんでおり、取引の規模が大きくなればなるほど、失敗した際の損失は多大なものになります。
M&Aで起こりうる失敗のパターンとして、どういったものがあるでしょうか?
当初の目的を達成できない
M&Aを通じて事業を買収あるいは売却しても、そもそもの目的を達成できないならば、そのM&Aは失敗ということになります。
例えば、後継者の不在に悩む中小企業の多くは、事業承継や会社の存続などを目的にM&Aを選択します。大企業の場合は、マーケットシェアの拡大やシナジー効果の創出、国際競争力の向上などを狙って、M&A戦略を策定するケースが多いでしょう
しかし、M&Aの相手が見つからず事業承継ができなかったり、マーケットをうまく拡大できなかったりする可能性はあります。
当初の目的が達成できなかった場合、また想定していた効果やメリットが得られなかった場合に、M&Aは失敗したと評価されます。
M&Aを検討する際は失敗する可能性をできるだけ低くするため、自社の置かれた状況や事業戦略との適合性を考慮し、しっかりと相手の情報を収集・精査した上でM&Aに臨まなければいけません。
マッチングや交渉の不成立
相手とのマッチングの失敗や、交渉が難航した結果、M&Aの話が立ち消えになってしまうのも、よくある失敗パターンとして知られています。
M&Aの検討段階では、まず価格や条件を設定して相手を選びます。しかし全ての条件を満たす理想的な案件は少なく、条件を満たしてもマッチングや交渉が成立するとは限りません。
本格的に交渉を始める前にマッチングが失敗したと分かれば、改めて違う相手を探すことはそれほど問題にはならないでしょう。
しかし、実際に費用のかかる買収調査(デュー・デリジェンス)の後にM&Aが成立しなければ、調査に費やしたコストや時間が無駄になってしまいます。
また、M&A自体は成立しても、後から問題やトラブルが発生した結果、当事者が大きな損失を被ったのであれば、結果的にM&Aは失敗だったと評価されるでしょう。
のれん代が減損してしまう
『のれん代』とは、買収企業の目に見えない部分の価値に対して、支払った対価を指します。
例えば、市場価格が50億円の事業を80億円で買収したとすると、差額の30億円が『のれん代』とみなされます。当該事業のブランドをはじめ、目に見えない価値を評価した金額ということです。
M&Aによる買収において、適正な金額を『のれん代』として算出するのは困難なのが実態です。買収した企業に想定した価値がなかった場合、後から『のれん代』の取り崩し(減損)を行わなければいけません。
買収額が大きいほど、買い手は多額の減損を抱えることになってしまいます。事実、買収対象の『のれん代』を適正に評価できなかったために、M&Aに失敗した事例は少なくありません。

投資費用を回収できない
M&Aによる買収後、景気が急激に落ち込んだり市場の変化があったりして、投資に見合った十分な効果が得られないケースもあります。
また、同じ事業を買収したいと考えるライバルが複数いる場合、事業の買収価格がつり上がってしまう可能性もあるでしょう。
さまざまな要因によって、買収対象の事業が実態以上の高値になってしまった結果、割高での購入になってしまう可能性があります。そうなると、投資費用に見合ったリターンが得られない事態にもなりかねません。
企業イメージを損なってしまう
買収した事業がコンプライアンス上のトラブルを抱えていたり、社会的評判を損なうような問題をはらんでいたりした場合、買収によって自社のイメージまで損なわれてしまう恐れがあります。
企業イメージが悪くなり、売上が下がってしまう事態になった場合、そのM&Aは失敗だったとみなされるでしょう。実際、M&Aの前には表に出てきていなかった問題・トラブルが原因で、買収側の評判が悪くなってしまった事例があります。
買収後に不正や粉飾などが発覚する
買収前の調査が不十分であったため、後から粉飾決算や簿外債務などが見つかり、予期せぬ損失が発生するケースもあります。
代表的な簿外債務としては、貸借対照表には計上されていなかった従業員への未払い給与や、残業代などが挙げられます。意図的に売り手の経営者が隠している場合もありますが、買収後に従業員が請求してくる可能性もあるでしょう。
さらに、会計上の違法行為が発覚した場合、世間に広まって自社の企業イメージが失墜してしまう恐れもあります。
破産に追い込まれてしまう
買収企業の抱えていた問題を発端として、破産に追い込まれる可能性もゼロではありません。M&Aの結果、買収側が破産してしまうケースはまれですが、莫大な債務を抱えた事業を買収した結果、もともとの事業の大きな負担になる事態は考えられます。
時間と手間をかけて買収したのにもかかわらず、その事業が慢性的な赤字体質で、改善の兆しが見られない場合もあるでしょう。実際、買収後に黒字化に転じられず、結局は廃業したり、事業を売却したりする結果になった事例もあります。
M&Aが失敗してしまう要因

『想定した効果が得られない』『予期せぬ損害が発生した』『投資資金を回収できない』といった失敗は、なぜ発生してしまうのでしょうか?原因を明らかにした上で、失敗を未然に回避するための対策を立てましょう。
M&Aに関する知識が足りない
M&Aの基本的な知識が足りない場合、十分な準備ができず交渉がうまく進まなかったり、後からトラブルを抱えてしまったりする可能性が高くなります。
特に中小企業や個人事業の場合、事業主が自らM&Aの交渉や手続きを進める場合がほとんどです。しかし、M&Aの流れを理解しておらず、準備に手間取るケースが少なくありません。
M&Aには一連のプロセスがあり、それぞれに注意すべき事柄があるので、基本的な流れとともに知っておく必要があります。
例えば、M&Aの検討段階では、経営戦略に基づいたM&Aの戦略をしっかりと立てることが重要です。対象会社を選定する際は情報収集を入念に行い、買収に伴うリスクを洗い出さなければいけません。
さらにM&Aの成立後は、事業の統合をスムーズに終わらせる必要があります。組織の再編や管理体制、企業風土の統合に失敗したり、従業員への説明が不足したりすれば、優秀な人材が流出する可能性があります。
M&Aで失敗するケースの多くは、各プロセスにおける計画やリスク対策の不備が原因です。トラブルになりやすい部分をあらかじめピックアップし、対処法を考えておかなければいけません。

対象とする業界の知見や知識が不足している
基本的な手続きに関する知識に加えて、買収する事業の業界に対する知見や知識が不足している場合も、失敗するリスクが高くなるので注意が必要です。
M&Aでは、自社の主力事業とは異なる分野の事業を買収し、新分野への進出を狙うケースも多く見受けられます。
新たな分野で成功を収めるには、その業界に対する一定の知見を有していなければいけません。その業界に関する情報収集を徹底しなければ、思わぬところで行き詰まる可能性があります。
例えば、エステ業界は顧客に対して、事前に回数券を購入してもらう『前払いビジネス』の世界です。回数券の存在に気付かず店舗を買収した場合、買い手は回数券の分だけ施術をしなければいけません。
こうした『隠れ債務』の存在を事前に知らなければ、買い手は大きなリスクや資金的な負担を背負うことになります。隠れ債務に関しては、以下の記事で詳しく説明しています。こちらも参考にしてください。

事業の価値を正しく評価できていない
売り手の事業価値を正しく評価しておらず、いわゆる『高値づかみ』をしてしまうケースも多くあります。上記の『のれん代』の減損や、投資金額を回収できないといった事態に陥ってしまった事例は少なくありません。
M&Aでは、少しでも安く買収したい買い手側に対し、売り手側はできるだけ高く事業を売却したいと考えているものです。
M&Aの価格の決まり方や相場感、価格交渉のポイントなどを把握していないと、売り手が提示する高めの価格設定を許容してしまう可能性があります。
『高値づかみ』を回避するには、売り手の企業価値評価をしっかりと行う必要があります。根拠のない価格設定をせずに、客観的な事実に基づいた評価を心がけましょう。
自社に事業評価のノウハウがなければ、M&Aを熟知した専門家の支援を受けることが大事です。

簿外債務を見逃してしまう
対象会社の簿外債務を見逃してしまった結果、買収後に買い手側の負担となってしまう事態は、M&Aではよく見られます。
M&Aで問題となる簿外債務としては、上記のように従業員への残業代の未払いをはじめ、回収の見込みがない売掛金や金融商品の含み損などもあります。
また、損害賠償請求が発生する可能性のある問題を、売り手事業が抱えている場合もあるので注意が必要です。さらに売り手側も想定していなかった偶発債務が、買収後に発生する場合もあります。

従業員の理解を得られていない
買収先の従業員の理解を得られておらず、経営者の交代をきっかけに従業員が大量に離職してしまったり、モチベーションの低下によって生産性が著しく下がってしまったりする場合もあります。
特に優秀な人材の流出により、想定していた知識やノウハウの引き継ぎがうまくいかず、当初の目的が達成できないケースは少なくありません。買収事業のキーマンが抜けてしまい、M&Aが失敗に終わってしまった事例もあります。
買収後の経営統合(PMI)に失敗する
M&Aの交渉は無事にまとまっても、買収後の経営統合(PMI)に失敗するケースも珍しくありません。
PMIとは『Post Merger Integration』の略語で、買収後の統合プロセスを指す言葉です。買収した事業と既存事業との経営上の統合に加えて、業務プロセスの統合、さらに企業風土や企業文化などの統合(意識統合)の三つの段階からなります。
もともと異なる事業同士の統合にはかなりの時間を要するので、一般的にはM&Aの交渉中に、統合後の計画もある程度は固めておかなければいけません。それを怠った結果、買収後の統合に大幅な遅れが出てしまうケースがよくあります。
PMIについて詳しくは、以下の記事で解説しています。こちらも参考にしてください。

M&Aの交渉時に起きたトラブル事例

M&Aの交渉場面では、両者の意見が食い違ったり、問題が発覚したりして交渉期間が長引く場合もあります。実際どのようなトラブルが起こりやすいのか、事例を交えて解説します。
譲渡金額の再交渉が必要になった
M&Aでは事業譲渡の方法(スキーム)や、取引価格などの基本的な事項を決定した後に、売り手と買い手の間で基本合意書を締結します。締結後は合理的な理由がない限り、内容が大幅に変更されることはありません。
価格の再交渉が行われるのは、基本合意に関して何らかの問題やミスが発覚した場合です。再交渉となればM&Aが成立するまでの期間が長引き、それだけコストもかかるため、契約の締結前に抜けや漏れがないか、よく確認することが大事です。
実際、譲渡価格の決定後にフランチャイズ加盟料が別途必要になる事実が判明し、価格の再交渉を余儀なくされた事例があります。
このケースでは売り手側の確認ミスが原因だったため、元の取引価格からフランチャイズ加盟料を減額することで話がまとまりました。
売り手側が事情を把握していないケースもあるため、気になる点や不明点があれば、納得がいくまで確認することが大事です。契約前の情報収集の重要性に関しては、以下の事例でも取り上げています。

契約締結後に赤字が判明した
M&Aの契約締結後に赤字が判明し、価格や条件の再交渉をせざるを得なくなった事例があります。
当初は、『黒字経営で後継者が不在』という点に引かれて買収を決めたものの、助成金を除くと数百万円の赤字が出ていることが発覚しました。M&Aの仲介業者が直近の売上資料を提供しなかったことが、判断ミスを招いたようです。
通常、売り手は買い手のリクエストに応じて自社の資料を提供しなければいけません。これらの資料は、価格や条件を決定する上での重要な材料となります。
交渉に不利になる情報を隠蔽する売り手や仲介業者もゼロではないため、買い手は慎重に交渉を進める必要があります。取引規模がそれほど大きくなくても、財務面・税務面のデュー・デリジェンスは実施するのが望ましいでしょう。
契約締結後に発覚した赤字を乗り越えた事例は、こちらで紹介しています。

交渉に時間がかかり過ぎた
交渉期間が長引けば長引くほど、M&Aが不成立に終わるリスクが高まります。売り手と買い手、双方のM&Aに対する熱意も冷めていくでしょう。交渉がスムーズに進まない理由としては、以下の理由が考えられます。
- 想定していなかったトラブルが発生した
- 仲介業者や売り手が交渉に必要な資料を提供してくれない
- 売り手と買い手が互いに希望する価格に大きなギャップがある
双方が提示する希望取引価格に差異があり、互いに一歩も譲ろうとしないというケースはよくあります。
明確な理由や根拠を示した上で希望価格を提示するのが一般的ですが、「このくらいの価値はあるだろう」といった思い込みに頼って価格を設定すると、交渉はなかなか前に進みません。
また、M&Aのマッチングサイトを使う場合、メールでのやりとりやWeb面談に不慣れだと、交渉や手続きにやや時間がかかるケースがあるようです。
M&Aの成立後に起きたトラブル事例
M&Aの成立前であれば交渉や契約のやり直しができますが、売り手に買収する事業の対価を支払った後では、基本的に取り返しがつきません。どのようなトラブルが起きているのか、なぜトラブルを未然に防げなかったのかを考えてみましょう。
キーパーソンが離職してしまった
経営者が変わった途端、売り手事業のキーパーソンの離職が相次ぐ場合があります。代替の利かない人材が次々と離職してしまうと、多額の費用をかけて事業を買収した意味がありません。最も重要な財産は『人』である点を忘れないようにしましょう。
キーパーソンの離職を防ぐ施策の一つとして、『リテンション・ボーナス(残留報酬)』が挙げられます。これは優秀な人材が自社に残ってくれた場合、特別な手当を支払う方法です。
まずはデュー・デリジェンスでキーパーソンを洗い出し、能力や性格を分析しましょう。優秀な人材やキーパーソンに対し、インセンティブや地位の確保などを約束した上でM&Aを進めれば、離職をある程度は防げるでしょう。
また、前の経営者を慕う従業員が多い中小企業では、経営者の交代と共に離職者が増える傾向があります。前経営者に顧問や会長などの形で残ってもらい、引き継ぎのサポートを受けるのも有効です。
重要な資産を引き継げなかった
事業譲渡では、売り手は売却資産と売却しない資産を選択できます。したがって、買い手は必ず思い通りの事業資産を引き継げるとは限りません。買い手は引き継げるものと引き継げないものを明確にした上で、最終契約を締結する必要があります。
実際、レンタルスペースのM&Aにおいて、事業は買収できたのにもかかわらず、オンライン予約サイトが引き継げなかった事例があります。当初は引き継ぐ予定でしたが、後になってサイトの権限が売り手にない点が判明したのです。
権限の所在を売り手自身が把握できていない場合もあるため、少しでも不明点がある場合は、明らかになるまで確認しましょう。

有名なM&Aの失敗事例

大手企業の場合、日本国内でもM&Aの事例が多くあります。個人事業や中小企業のM&Aとは規模感がまったく異なりますが、失敗事例から学べることは多いでしょう。
ここでは、有名な大手企業がM&Aによる事業買収後、トラブルで大きな損失を被った事例を紹介します。
DeNAによるキュレーションサイトの買収
株式会社ディー・エヌ・エー(以下、DeNA)は、モバイルゲームの開発や配信を主業とするインターネット関連企業です。
2014年に、同社はキュレーションメディア事業に参入するべく、メディア事業を営むiemo株式会社と株式会社ペロリの買収に踏み切りました。
しかし、買収した運営サイトの一つに、信ぴょう性に欠ける情報や著作権を侵害する記事があったことで、世間の批判を浴びることになります。その結果、企業イメージの低下を招いただけでなく、巨額の減損損失を計上する結果になりました。
企業価値評価やデュー・デリジェンスを徹底しなかったことが、M&Aによる買収の失敗につながったといえるでしょう。
※参考: 全10サイト非公開化でDeNAが謝罪『成長を追い求める過程で』|THE PAGE
東芝による原子力事業会社の買収
2006年に大手総合電機メーカーの株式会社東芝(以下、東芝)は、当時これからの主力事業と考えていた原子力発電の基盤を築くため、アメリカの原子力事業会社ウェスチングハウスの買収に踏み切りました。
54億ドルもの巨額を投じて買収したものの、2011年の東日本大震災の発生によって原子力発電の安全性に疑問が投げかけられる事態となり、さらに買収先が巨額の赤字を抱えていたことが明らかになります。
東芝は同企業の買収において、3,300億円を『のれん代』として計上していましたが、結果的に2,600億円もの減損が発生し、東芝自体も債務超過に陥ってしまいました。
東日本大震災というイレギュラーな事態はあったとはいえ、買収先の調査不足と『のれん代』を過剰に評価してしまったことなどが、失敗の原因とされています。日本国内で最も有名なM&Aの失敗事例の一つです。
※参考: 東芝のスポンサー選び大詰め。判断ミス2回、3度目の正直なるか|日刊工業新聞電子版
キリンによるビール会社の買収
2011年にキリンホールディングス(以下、キリン)は、海外に本格的に販路を築くため、ブラジルの大手飲料メーカーであるスキンカリオール社を買収しました。
当時のブラジルの経済成長は著しく、有望な市場と考えられていましたが、買収後に景気が急激に悪化してしまいます。
キリンは当初期待していた成果を上げられず、さらに1,100億円もの減損が発生したこともあり、約470億円もの損失を計上しています。結局、買収した子会社もオランダの企業に売却することになり、M&Aの有名な失敗事例の一つとなりました。
※参考: キリンがブラジルのM&A失敗で2,000億円の損失、原因は?|M&Aファイナンス新聞
第一三共による医薬品メーカーの買収事例
日本を代表する大手製薬会社の第一三共株式会社(以下、第一三共)は、2008年にインドのハリヤーナー州を本拠地とする、製薬会社ランバクシー・ラボラトリーズを4,884億円で買収しました。
この金額は同社の前期の現金および現金同等物の金額に匹敵するほどで、業績拡大やシナジー効果が発揮されなければ、投資回収が難しいという見方もあったようです。
買収合意の直後、品質管理に問題があるとして、ランバクシー社の後発薬が米国で輸入禁止措置を受ける事態になります。
その後わずか半年で、ランバンクシー社の株価は暴落し、第一三共は巨額の特別損失を計上する結果となりました。結果的に2014年、同社はランバクシー社の実質的な売却を決定しています。
海外企業とのM&Aは国内に比べて情報収集が難しい上に、法規制や商習慣が異なります。情報収集が十分でない場合、失敗のリスクが高まるでしょう。
※参考: 第一三共、失策続きの6年 印子会社を実質売却|日本経済新聞
想定していた効果が得られなかった事例

M&Aでは、当初想定していた成果が上げられない場合も少なくありません。十分な投資効果が得られなければ、高額な買収資金が無駄になり、経営に大きな打撃を与える可能性があります。
日本および海外の大手企業の買収案件で、想定していた効果が得られなかった事例を見てみましょう。
RIZAPグループ
RIZAPグループ株式会社(以下、ライザップ)は、パーソナルトレーニングジムの運営や化粧品・健康食品の販売などを行う子会社を統括する持株会社です。
ライザップには、赤字企業を安く買収して経営を立て直し、短期間で収益を拡大させるという経営戦略があります。実際、積極的な企業買収によって急成長を遂げましたが、2019年3月期に194億円の最終赤字に転落してしまいました。
これは経営の立て直しが十分に行われないまま、赤字企業を買収し続けたためで、結果としてグループ全体の業績が傾く結果となりました。現在は本業に注力すべく、赤字企業を整理する方向で動いています。
※参考: ライザップ、純損失193億円に転落 子会社不振|朝日新聞デジタル
リクルート
株式会社リクルートホールディングス(以下、リクルート)は、人材派遣やITソリューション、求人広告などのさまざまな事業を手がける企業です。リクルートグループを統括する持株会社で、連結子会社は271社にも上ります。
同社は2013年、アメリカ国内における不動産ビジネスを拡大させるため、同国の中古不動産情報サイトを運営するMovoto LLCを買収しました。しかし、その4年後の2017年には、ベンチャーキャピタルを率いる堀口雄二氏に全株式を譲渡しています。
買収当初、リクルートは日本やアジアで培ってきた知見やノウハウが活用できると考えていました。ビジネスノウハウの有効性を米国市場で検証するという目標は達成できたとはいえ、競争環境を考慮すると売却が賢明と判断したようです。
海外展開を考える際は、自社のノウハウがどう生かせるかを十分に調査する必要があります。日本やアジアで成功したからといって、全世界で通用するとは限りません。
※参考: 過去の失敗から学ぶ M&Aのポイント | Campaign Japan
グリー
グリー株式会社(以下、グリー)はゲーム・アニメ・SNSなどを手がけるインターネット関連企業です。
スマホ向けゲームの開発力を強化するため、モバイルソーシャルアプリの企画・開発・運営を行う株式会社ポケラボ(以下、ポケラボ)を、2012年に約138億円で買収しました。
買収の翌年は売上を伸ばしましたが、徐々にスマホゲームのトレンドに変化が起こり、2014年以降は売上が大きく下落します。2015年にはポケラボの買収額とほぼ同じ130億円の評価損を計上し、買収は失敗したかのように思われました。
しかし、ポケラボは2018年6月期より黒字回復を見せています。約11億円の赤字から、約10億円の黒字へと大きく転換し、グリーの増益に貢献しています。
※参考: 【グリー】非ゲーム事業でM&Aも、巻き返しなるか | M&A Online
M&Aが失敗する確率は?

ここまでM&Aのさまざまな失敗例を紹介してきましたが、実際のところM&Aが失敗してしまう確率はどれぐらいなのでしょうか?海外と国内で成功率にかなりの違いがありますが、いずれにしてもM&Aによる企業買収の成功率は決して高くはありません。
買収の成功率はかなり低い?
メディアではM&Aの成功例が報じられることもありますが、実際はこれまで紹介してきた事例も含めて、M&Aの失敗例は非常に多いのが実態です。
M&Aの成功率は事業規模や業界にもよりますが、約3~4割ほどとされています。つまり10件あるM&A案件のうち、6~7件は失敗に終わってしまうわけです。
ただし、何をもって成功・失敗とみなすかは、基本的にM&Aを実行した企業の考え方によるため、判断が難しいところでもあります。
いずれにしても、M&Aは失敗に終わる可能性が高いことを前提として、しっかりと戦略を立てて慎重に進めなければいけません。
海外企業を買収した際の成功率は1~2割程度
M&Aの成功率は全体としては3~4割程度ですが、日本企業が海外の企業をM&Aによって買収した際の成功率は、約1~2割しかないとされています。
上記の事例でも取り上げましたが、有名な国内の大手企業でも、海外企業の買収にかなりの確率で失敗している状況です。
クロスボーダーのM&Aの成功率が著しく低い理由としては、言語の壁があって相手とコミュニケーションを取りづらく、必要な情報を入手しづらい点や、物理的な距離があるため、十分なPMIができないといった点などが挙げられます。
また、カントリーリスクも考慮しなければならず、想定外の出来事により大きな損失が出てしまうケースも珍しくありません。
成功例もあるので失敗率だけに注目すべきではありませんが、国内企業同士のM&A以上に、じっくりと時間をかけて調査をした上で、慎重に判断しなければいけません。
失敗しないためのM&Aの進め方

いかに時間と手間をかけて準備をしても、M&Aには失敗のリスクが付きまといます。ですが、以下のポイントを押さえながら戦略を立てれば、失敗の確率を減らすことが可能です。M&Aの進め方のポイントを押さえておきましょう。
戦略の立案
まずは目的を明らかにした上で、しっかりとM&Aの戦略を立てる必要があります。
事業を買収する場合は、買収後の方針をしっかりと示し、どういった経営資源を獲得すれば、どのような効果が得られるのか明確にしましょう。M&Aを通じて自社の事業戦略を実現できるか、慎重に判断しなければいけません。
M&Aはあくまでも事業戦略を実現するための手段の一つなので、もし買収以外の選択肢で目的を達成できるならば、そちらも検討する必要があります。
ターゲットの選定
M&Aの対象となる会社あるいは事業について、入念なリサーチをした上で相手をリストアップしていきます。相手方にM&Aの意思があるとは限らないので、基本的には複数の会社にアプローチすることになるでしょう。
相手を選ぶ際には売却ニーズに加えて、自社の事業とのシナジーが見込めるか、将来性はあるかなど、さまざまな観点から評価をしなければいけません。
事前のリサーチ不足で失敗に終わった例は多いので、必要に応じて専門家の意見も取り入れながら、候補を絞り込んでいきましょう。
企業価値の評価
M&Aの対象会社を決めたら、相手の企業価値を算定します。ここでも相手の価値を見誤った結果、実際よりも高く事業を購入してしまった例や、過度な『のれん代』を算定したために、後から減損を計上した例もあるので注意しましょう。
企業価値の算定には、株式市場での価値を基準に評価する方法(マーケット・アプローチ)や、収益力を基準とする方法(インカム・アプローチ)、純資産額をベースに価値を判断する方法(コスト・アプローチ)が用いられます。
いずれかの方法を選択する場合もありますが、それぞれの観点からしっかりと調査を実施することをおすすめします。それぞれのアプローチを通じて、できる限り正確に対象会社の価値を見定めましょう。
デュー・デリジェンス(DD)
『デュー・デリジェンス(買収調査)』とは、M&Aの相手のビジネスや財務・法務の状態などを調査することです。企業同士のM&Aの場合、一般的に専門家に協力してもらいながら、安全性やリスクに関する情報を把握します。
調査できる時間は限られているので、事前のプランニングが極めて重要です。失敗に終わらないためにも、M&Aの初期段階から計画と準備を進めておく必要があります。
M&Aの検討段階で実施されるデュー・デリジェンスに関して、詳しくは以下の記事で解説しています。こちらを参考にしてください。

クロージング後のPMI
M&Aが無事に完了しても、PMIを適切に実行しなければ事業の統合がうまくいかず、結局は失敗に終わってしまうでしょう。
異なる事業同士が統合されるM&Aでは、必ず現場で何らかの混乱が発生します。混乱を最小限に抑えつつ、スムーズに事業運営を進められるような工夫が求められます。
特に買収後の3~6カ月は重要といわれているので、この期間に集中して組織体制や業務プロセスなどを統合できるように、M&Aの交渉を進めている段階で準備をしておくことが大事です。
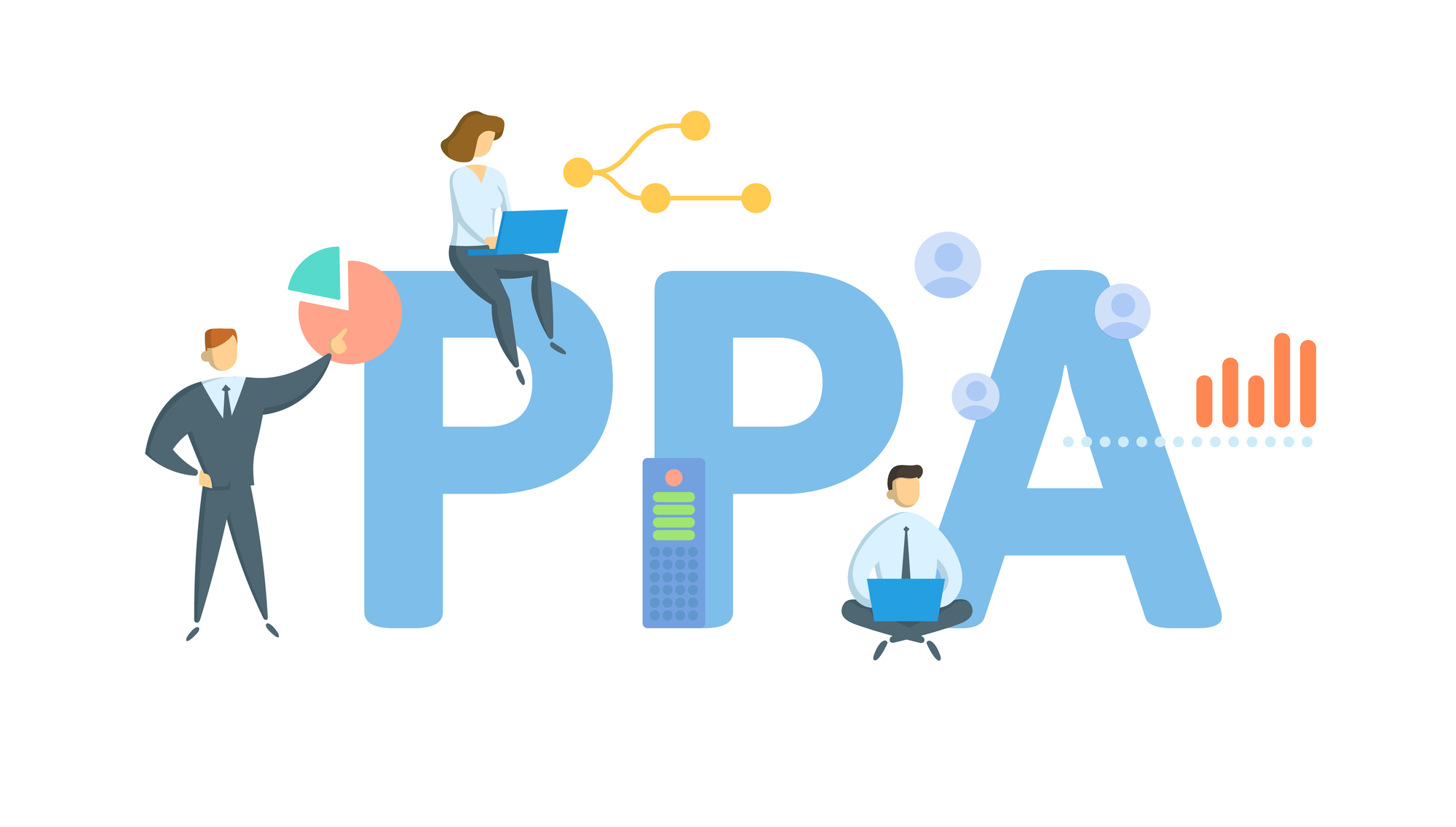
M&Aの成功事例も知っておこう

最後に、M&Aの成功事例も参考にしてみましょう。いずれもM&Aのプラットフォームである『TRANBI』の事例です。
『TRANBI』は2,000件以上のM&A案件を掲載しており、未経験者による成約率が約75%と非常に高いのが特徴です。中小企業はもちろん、個人事業主の利用もおすすめなので、この機会に会員登録してみましょう。


愛知県で実現した自動車業界のM&A
自動車開発における機械設計やCAD設計、制御ソフトなどの開発を手がけるT社は、「エンドユーザーとの接点」や「車好きの社員が集まる場を作りたい」といったニーズから、高級車の付属パーツや中古車の販売を手がけている会社を買収しました。
同企業は後継者の不在に悩んでおり、トップ同士の話し合いで互いに好印象を抱いたことなどから、スムーズに買収の話が進んでいます。
買収後は現場を見ることでお客様のニーズを吸い上げたり、社員の憩いの場・チームビルティングの機会として活用しているとのことで、成果を実感しているようです。
事前にどういった会社を選択すべきか、自社の事業との整合性やシナジーを考慮した上で、明確に条件を設けていたのが成約できた要因です。

M&Aで東南アジア市場の開拓に成功
コンサルティングを通じて、マーケティングのデジタル化を支援してきたアンダーワークス社は、シンガポールでデジタルマーケティング関連サービスを提供している会社を買収しました。
かねてから事業のグローバル展開を考えていた同社は、マッチングサービスを通じて同じ業態・事業規模の買収対象を探し、シンガポールという条件でのクロスボーダーM&Aを成功させています。
基本合意書を締結するまで10回ほど話し合いを重ねる必要があったのですが、緻密な計算をもとに買収金額を交渉したことで、無事に話がまとまったようです。
海外企業のM&Aの成功率が低いのは事実ですが、自社事業とのシナジーや将来性を入念に調査し、粘り強く交渉することで、成功に結びつけられることが分かる事例といえるでしょう。

まとめ
近年は大手企業だけでなく、中小企業や個人の間でもM&Aが盛んに行われています。参入障壁が低くなり、気軽に挑戦できるようになったのは歓迎すべきですが、安易なM&Aは失敗を招きます。
基本的な流れやポイントを押さえた上で、できるだけ多くの事例に触れ、成功のヒントや失敗を回避するコツを学びましょう。
『TRANBI』では、成約・成功事例インタビューを紹介しています。成約に至るまでの苦労話もあり、これからM&Aにチャレンジする人の参考になるはずです。M&Aの事例は以下でも詳しく紹介しています。









