
M&Aの価格の相場はいくら?一般的な評価方法や価値を決める要素
M&Aの成約価格の相場は、業種や規模によって異なります。価格はどのように決まるのでしょうか?中小企業のM&A価格を決める際、参考として用いられる算出方法や、価格を左右する要素を確認しましょう。買収の可否の判断に役立つ指標も紹介します。
「TRANBI」は、ユーザー登録数10万人以上を誇る国内最大級のM&Aプラットフォームです。豊富な成約・成功実績を持つ当社では「各種契約書の雛型」や「買い手向けガイド」を用意し、スムーズなM&Aの実現をサポートしています。まずは、無料会員登録をしてM&Aに役立つ資料をダウンロードしましょう。

M&A価格はどのように決まるのか

M&A価格の決め方に特別な決まりはなく、売り手と買い手の合意によって決定します。入札方式の特徴や業種・規模による違いを確認しましょう。
売り手と買い手の交渉で決まる
売り手と買い手の交渉によって決まるのが、M&Aにおける価格の基本です。二者間で合意に至った価格で契約が交わされるため、はっきりとした相場はありません。
交渉をする際には、まず売り手が価格を提示するのが一般的です。このとき対象企業への思い入れの強さから、売り手は企業価値を高く見積もりがちです。
一方、買い手はよりお得に買収したいという考えから、値引き交渉を行うケースもあります。価格についての考え方に折り合いがつかなければ、交渉が成立しないかもしれません。
入札方式の場合
対象企業1社に対し複数の買い手候補が現れると、『入札方式』で価格が決定するケースもあります。買い手候補が買収価格やM&Aスキーム・経営方針などの条件を提示し、その中から売り手が選ぶ方法です。
売り手が売却先を選ぶ上では、価格以外の条件も加味して決められます。そのため、必ずしも高い買収価格を提示した買い手が選ばれるとは限りません。競売のように、どんどん価格がつり上がっていくとは考えにくいでしょう。
ただし買い手が価格を重視して決定する方針であれば、比較的高額になりやすい方式です。
業種や規模による違い
M&A価格は売り手と買い手の交渉で決まります。ただし金額が大きくなりやすい案件もあるため、自分の予算で買収できるか把握するには、業種や規模をチェックするとよいでしょう。
例えば以下の業種であれば、数百万円で買収できる案件が多く出ています。
- 学習塾
- 飲食店
- サロン・エステ店
- Webサービス
- 介護事業
M&Aマッチングプラットフォームの『TRANBI(トランビ)』で過去にM&Aが成立した案件にも、洋菓子店800万円・飲食店500万円・リラクゼーションサロン230万円といったケースがありました。
一方でM&A価格が高額になりやすいのは製造業です。大規模な機械設備が必要な業態であるほど、高額になりやすいでしょう。
少額のM&A案件を探すときに役立つ知識を解説している以下も、ぜひご覧ください。


適切な価格を知ることが重要

本来の価値より高い価格で買収する高値づかみは避けたいものです。しかし値引き交渉にこだわり過ぎると交渉が成立しません。まずは適切な価格を知ることが重要です。
企業価値評価やデュー・デリジェンス(DD)の実施により、交渉のベースになる適切な価格を把握しましょう。
M&Aの際は企業価値評価を行うのが一般的
M&A価格は交渉によって決まりますが、交渉の前にベースとなる金額を算出する企業価値評価を実施するのが一般的です。中小企業は上場していない場合が多く市場価値が分からないため、企業価値評価を行います。
企業価値評価の手法は、以下の3種類が代表的です。
- マーケット・アプローチ:対象企業に類似している上場企業の株価を参考に算定
- インカム・アプローチ:対象企業が将来得ると期待される収益の現在価値で算定
- コスト・アプローチ:対象会社の決算書に記載されている純資産価格により算定
業種によっては、対象会社を訪問し、実際に直接会社を見て評価する、『実査査定法』を取り入れてもよいでしょう。どれか一つではなく、複数の評価方法を用いて評価します。
DDなどで高値づかみによる失敗を防ぐ
契約が成立しても、高値づかみをすると事業が軌道に乗るまでに破産に陥る可能性もあるでしょう。高値づかみの失敗を防ぐには『デュー・デリジェンス(DD)』や『アーン・アウト条項』が役立ちます。
DDは、対象会社に対して買い手が行う調査です。財務・税務・法務などさまざまな分野ごとに専門家へ依頼し、対象会社の実態を調べます。正しく現状を把握することで、適正価格を提示できるでしょう。
対価の一部を買収後の成果によって支払うことを定めるアーン・アウト条項も有効です。クロージング時に支払う対価を限定することで、買い手は高値づかみに陥るリスクを避けられます。
DDについて解説している以下も、ぜひご覧ください。


中小企業のM&Aでよく使われる価格算出方法

企業価値評価を実施する際、中小企業では『年買法』がよく用いられます。年買法の計算方法や、算出に用いられる『のれん(営業権)』について紹介します。
時価純資産+のれん(営業権)
年買法を用いると『時価純資産+のれん(営業権)』というシンプルな計算式で、企業価値を算出できます。
企業価値評価では、複雑な計算が用いられるケースも多く、自力での算出が難しい場合には、専門家に依頼する必要があります。しかし年買法であれば直感的に理解でき、計算式も簡単です。自力でも計算しやすいため、中小企業でよく用いられる方法です。
のれん(営業権)とは
シンプルな計算式で企業価値評価を行える年買法では、時価純資産にのれん(営業権)をプラスします。のれん(営業権)は『買取価格-時価評価純資産』で算出される金額です。
企業の持つ資産には有形資産と無形資産があり、有形資産は帳簿を見ると価格が記載されています。一方、以下に挙げるような無形資産の価値は、どこにも記載されていません。
- 取引先との関係性
- ノウハウ・技術
- 人材
- 企業風土
- ブランド力
- 信用力
この無形資産の価値がのれん(営業権)に相当します。売り手が築き上げてきたこれらの資産に魅力を感じると、買い手は確実に買収するために高額な『買収プレミアム』を設定するケースもあるでしょう。


付加価値を高める会社の財産の例

『顧客リスト』や『従業員の技術』など、付加価値として扱われる財産を対象会社が持っていれば、M&A価格は高くなる傾向があります。ただし重視される財産はM&Aの目的によって異なるため、この財産があるから一概に付加価値が生じるとは限りません。
ブランド力・立地などM&Aの目的で異なる
付加価値がプラスされるかどうかは、M&Aの目的によって決まります。例えば介護事業を始めたいけれど許認可を得るまでの期間が長く、それまで収益を得られないのが課題だとします。
この場合、既に許認可を得ている会社を買収できれば、課題の解決が可能です。許認可があれば初月から収益を上げられるため、その分、付加価値があると考えられるでしょう。
ほかにも『ブランド力』『立地』『特許』などは、付加価値につながりやすい財産です。買い手がM&Aの目的を達成できる対象会社であれば、赤字でも買収価格は高額になりやすいでしょう。
優良な顧客・取引先リスト
『顧客リスト』や『取引先リスト』の獲得を目的にM&Aを実施する買い手もいます。新規事業に取り組む場合、顧客や取引先が既にあり関係性が構築されている状態であれば、事業を軌道に乗せやすいでしょう。
顧客や取引先を獲得するための施策が必要ないため、そのためのコストや手間もかかりません。買収直後から売上の見込みを立てやすくなるのも特徴です。早い段階で事業を安定させられる可能性が高まるため、高評価につながりやすい財産といえます。
従業員の数や技術
技術やノウハウを身に付けている『従業員』も、高く評価されやすい財産の一つです。少子化が進行している中、優秀な人材の確保はどの会社でも課題となっています。
人材を採用できたとしても、技術や知識の習得には研修が必要です。業務に必要な能力を身に付けるまでにコストも時間もかかります。
M&Aで優秀な人材を獲得できれば、新たに事業を始める場合でも、買収した翌日から滞りなく業務が回るでしょう。また事業規模の拡大を目的としたM&Aであれば、買い手企業の課題を解決できる人材の確保により、売上アップが期待できます。
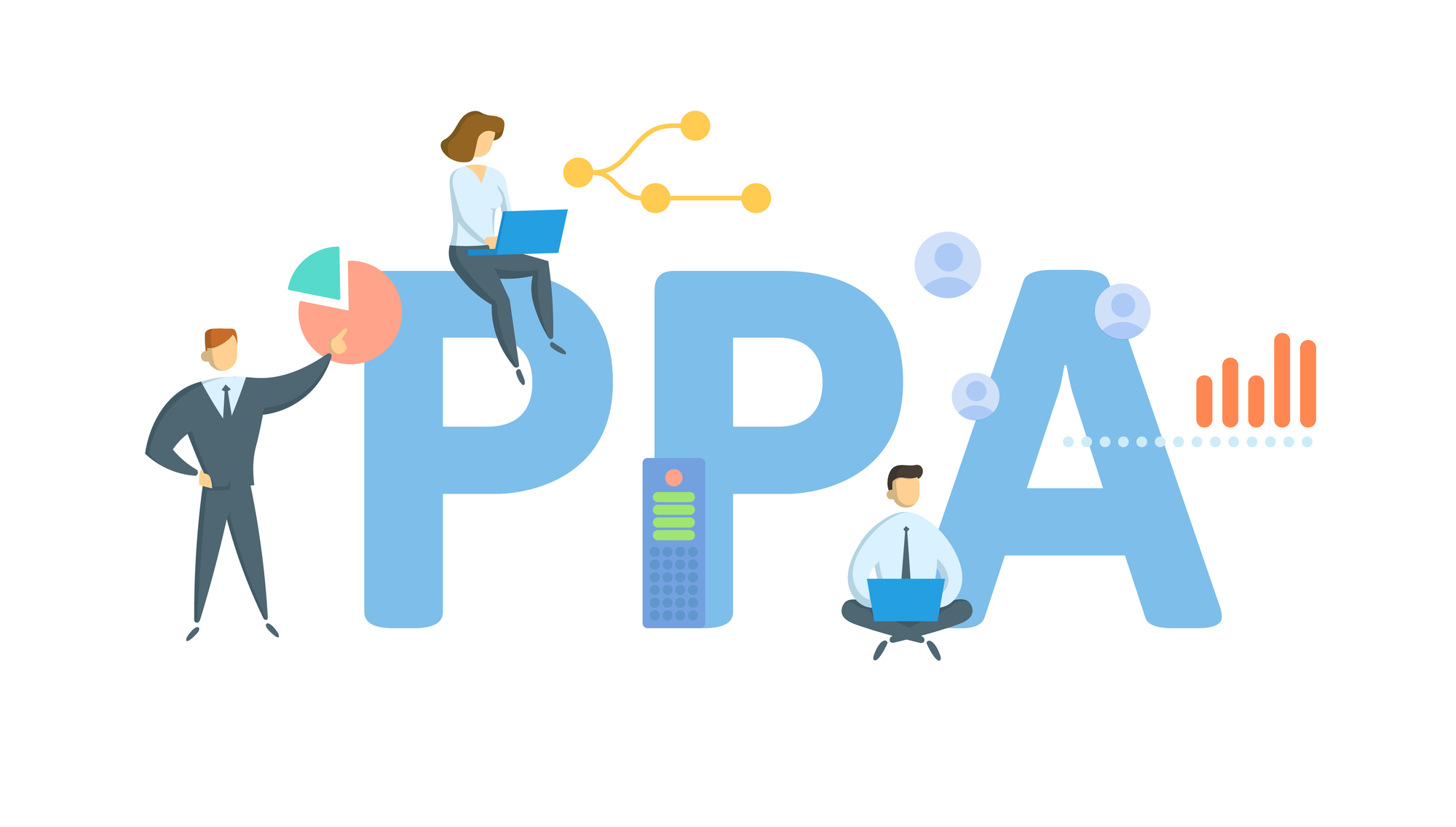
取得する株式の数や特徴による価格の増減

株式譲渡でM&Aを実施する場合、買い手が取得できる株式の『数』や『特徴』が価格に影響を与えます。支配権に対して支払う『支配権プレミアム』や、市場で売買できない流動性の低さに対する値引きである『非流動性ディスカウント』が代表的です。
支配権プレミアム
M&Aにより対象会社の株式を取得し支配権を得るには、支配権プレミアムを価格に上乗せするのが一般的です。支配権を行使すると会社の重要な意思決定を単独で行えます。
会社の経営を掌握できる状態には価値があると考えられていることから、行われる上乗せです。その分M&A価格は少数の株主の価値に比べて高額になります。
非流動性ディスカウント
中小企業のほとんどは株式を上場しておらず、市場での自由な売買の対象外です。そのため売却して現金にするには追加のコストがかかります。このコストを見越し、M&A価格から差し引かれる値引き額が、非流動性ディスカウントです。
20~30%の値引きが行われるケースがほとんどですが、具体的な割引率は個別に検討しなければいけません。


買収の判断に使われる指標

対象会社を買収するか判断する目安として『EV/EBITDA倍率』を知っておくと役立ちます。計算により求められた数値は何を表すのでしょうか?M&Aの参考になる指標をチェックしましょう。
EV/EBITDA倍率
M&Aの買収にかかったコストの回収に必要な期間を表すのがEV/EBITDA倍率です。例えばEV/EBITDA倍率が3であれば、3年分の利益でM&Aのコストを回収できる見込みがあります。低ければ低いほど、高い成果を得られる投資といえるでしょう。
EV/EBITDA倍率がいくつ以下で「買収する」と判断するかは、買い手によって異なります。状況によって10以下であれば買収するという買い手もいれば、2以下が望ましいと考える買い手もいるでしょう。
計算方法
EV/EBITDA倍率の計算式は『EV(株式時価総額+有利子負債−現預金)÷EBITDA(営業利益+減価償却費)』です。例えば以下のケースで計算してみましょう。
- 株式時価総額:1億円
- 有利子負債:3,000万円
- 現預金:2,000万円
- 営業利益:4,000万円
- 減価償却費:1,500万円
計算式に当てはめると『(1億円+3,000万円-2,000万円)÷(4,000万円+1,500万円)=2』と算出できます。この会社を買収した場合、2年でM&Aのコストを回収できる見込みです。

買収価格以外にM&Aで発生する費用

M&Aを実施する際には、買収価格以外にもコストがかかります。例えば案件を探すために利用する仲介会社の報酬や、サポートを依頼する専門家への報酬です。
仲介会社への報酬
会社を買収するときには、案件の紹介を行っている仲介会社を利用するのが一般的です。仲介会社への報酬は、M&Aの取引金額に定められた料率を掛けて算出する、レーマン方式を用いるケースが多いでしょう。
そのためM&A価格によっては、報酬として数千万円といった高額の支払いが発生します。案件の紹介に対する報酬を抑えるには、『TRANBI(トランビ)』のようなM&Aマッチングプラットフォームを利用するとよいでしょう。
掲載されている中から条件に合う案件を探し、直接売り手へ交渉を申し込めます。案件探しは無料プランで実施可能です。交渉したい案件を見つけたら有料のプレミアムプランへ加入します。有料のプランに加入することで、成約報酬手数料が一切かからないことが仲介会社と異なる大きなメリットとなっています。
専門家への報酬
対象会社をよく知った上でM&Aを実施するためには、DDといった調査が重要です。財務・税務・法務・労務など専門分野ごとの調査は、自力で行うと漏れが生じる可能性があります。
買収前に現状を正しく把握するには、税理士・弁護士・社労士などへ依頼するとよいでしょう。報酬金額は調査の範囲によって異なり、数十万~数百万円かかります。例えば簡易的な財務DDであれば20万円ほどです。



まとめ
M&Aの価格は売り手・買い手の交渉で決まるため明確な相場はありません。そこで適切な価格で買収するため、企業価値評価で算出した価格を基に交渉するのが一般的です。
加えて顧客や人材など買い手にとって魅力的な無形資産がある場合には、その分の価格を上乗せします。株式価格も同様で、支配権を行使できる3分の2以上保有できる場合には、支配権に対する価値を支配権プレミアムとして支払います。
一方、中小企業の株式は上場しておらず流動性が低いため、流動性ディスカウントという値引きが行われるのが一般的です。また最終的に買収を判断する基準として、EV/EBITDA倍率を活用するとよいでしょう。






