
IM(企業概要書)のM&Aにおける重要性とは。主な6項目と内容
M&Aの準備段階では、対象企業の事業内容や財務状況などを記した『IM(企業概要書)』が開示されます。買い手と売り手にとって、IMはどのような意味合いを持つのでしょうか?IMの重要性や記載される内容について解説します。

IM(企業概要書)とは

M&Aを検討している人の中には、『IM』という用語を見聞きしたことがある人も多いのではないでしょうか?IMは、『Information Memorandum』の頭文字を取ったもので、日本語では『企業概要書』と訳されます。
対象会社の情報が記載された資料
M&Aを始めるに当たり、買い手は売り手の企業情報をチェックした上で、買収先候補を絞り込みます。初期段階においては、M&Aの仲介会社によって『ノンネームシート』または『ティーザー』と呼ばれる企業の一次情報が開示されます。
ノンネームシートは、売上規模や地域、事業内容などが簡易的に記された概要書です。ノンネームという名前が示す通り、企業名は明かされません。
一方、IMは買収先候補の絞り込みの後に提出されるものです。ノンネームシートとは違い、企業名・所在地・ビジネスモデル・財務情報などが詳細に記載されています。


IMを取り交わす流れ

M&Aは、大きく『交渉準備』『交渉』『最終契約』のフェーズに区別されます。IMは交渉準備の段階において、売り手とM&Aアドバイザーが作成するものです。IMを取り交わすまでの流れを見ていきましょう。
秘密保持契約締結後に開示される
M&Aではさまざまな企業の機密情報が開示されます。売り手と買い手のマッチング後はすぐに交渉をスタートさせるのではなく、第三者に情報を漏えいしないことを定めた『秘密保持契約(NDA)』を締結するのが通常です。
IMには企業の重要な機密情報が記載されるため、NDAの締結前に開示されることはありません。
1.買い手がノンネームシートを確認する
2.秘密保持契約を締結する
3.買い手にIMが開示される
仲介会社を通さずに『入札方式』で交渉する場合は、NDAを締結した後、入札に関する資料(プロセスレター)と一緒にIMが配布されます。
IMを基に買い手は交渉を進めるか検討
売り手にとってのIMの目的は、買い手に自社の詳細情報を伝え、M&Aを検討してもらうことです。
買い手はIMを基に交渉の可否を検討するため、情報は正確でなければなりません。数値をただ並べるだけでなく、自社の優位性や魅力、M&Aに対する熱意を盛り込む点も重要です。IM=会社の履歴書と考えると分かりやすいでしょう。
買い手はIMを細かくチェックし、『サービスの優位性は何か』『利益を上げる仕組みはどうなっているのか』『自社とのシナジー効果は見込めそうか』などを分析し、交渉フェーズに進むかどうかを判断します。



IMはどのように作られるのか

IMは、M&Aの交渉段階における重要な資料の一つです。売り手はアピールポイントを漏れなく伝えると同時に、企業の情報を正確に記載しなければなりません。IMは誰がどのように作成するのでしょうか?
主にM&Aアドバイザーが作成する
IMの作成は、売り手側のM&Aアドバイザーが作成するケースが大半です。M&Aアドバイザーとは、売り手または買い手のどちらか片方と契約を結び、クライアントの利益の最大化に向けたアドバイスを行うプロフェッショナルです。
売り手自らが簡易的なIMを作成するケースもありますが、IMの精度によって交渉の可否が決まるため、プロの手を介した方が安心できるというのが一般的な考え方です。
IMの内容について、何をどこまで開示するかは売り手側に委ねられます。交渉前の段階においては、『売り手のアピールポイント』が大部分を占めると考えた方がよいでしょう。買い手はデータの正確性や虚偽の有無を精査しなければなりません。
エグゼクティブ・サマリーとは
IMの構成要素の一つに『エグゼクティブ・サマリー』があります。これは、買い手のエグゼクティブ(企業幹部)に必ず目を通してほしい内容を簡潔にまとめたもので、IMの冒頭部分に記載されます。
買い手の経営者の中には、資料の全てに目を通すのが難しい多忙な人もいます。冒頭に1~2ページのエグゼクティブ・サマリーがあることで、隅々まで目を通さなくても対象企業のアピールポイントを容易に理解できるのです。
同時に、その後に続く詳細内容のガイドラインの役割も果たします。売り手にとっては、自社の魅力を伝えるための最重要項目といっても過言ではないでしょう。



買い手の判断材料となる情報を記載する

ここからはIMに記載される項目を一つずつ解説していきます。全体像を分かりやすく伝えるため、実際のIMにはグラフや表、画像などが用いられるのが一般的です。
会社概要
多くの場合、『会社概要』はIMの1ページ目に記載します。企業名や所在地、資本金など、登記簿謄本に記載される内容とほぼ同じと考えてよいでしょう。会社設立後に移転や支店の開設などがあった場合、その内容も細かく記載します。
- 企業名
- 所在地
- 設立年月日
- 代表者名
- 資本金
- 支店数
会社のプロフィールに当たる部分なので、記載情報に誤りがないように注意しましょう。買い手は会社概要を踏まえた上で、その後に続く詳細内容を確認していきます。
組織、株主構成
次に記載されるのが、『組織に関連する事項』です。会社概要をさらに深く掘り下げたもので、会社の沿革や株主構成、組織図などが記載されます。
- 沿革
- 代表者のプロフィール
- 役員のプロフィール
- 組織図
- 株主構成
- 従業員数
- 従業員の情報
- 許認可の取得
株主構成には、株式の種類や株主名、持株比率まで正確に記載します。M&Aは株式譲渡で行われるケースが多く、『誰がどのくらいの株式を保有しているか』は買い手の大きな注目点となるためです。
従業員については、従業員数の推移や平均給与、平均年齢、有資格者なども記載します。
財務状況
冒頭のエグゼクティブ・サマリーにおいて、財務状況は重要な点のみをピックアップして記載しますが、財務状況の項目には、直近数年間の損益計算書や貸借対照表を掲載し、企業の実態を正確に伝える必要があります。
- 損益計算書
- 貸借対照表
- 資産
- 負債
- 借入状況(残高・年間返済額など)
資産や負債に大きな変動があった場合は、その理由を記載します。『大きな赤字が出た理由は何か』『急激に売上が伸びたのはなぜか』など、買い手から質問が出る可能性が高いためです。
買い手は、年間の数字の推移をチェックしたり、同業他社と比べたりして、経営が健全かどうかを判断します。
事業概要
事業内容には『ビジネスフロー』を記載します。ビジネスフローとは、事業の内容を分かりやすく可視化したもので、主に以下のような項目が盛り込まれます。
- 資金の流れ
- 商品の仕入先
- 取引の流れ
- ターゲット
- 客単価
- セールスポイント
- 販売チャネル
- 業界・地域におけるポジション・役割
- 自社の優位性・独自性
複雑な事業内容を文字だけで説明するのは難しいものです。写真やグラフ、図などを盛り込むと、買い手がビジネスモデルのイメージをつかみやすくなるでしょう。
事業計画
事業計画は、事業を進めていく上ではもちろん、銀行や投資家から融資を受けるために欠かせないものです。短期計画は1年以内、中期計画は3〜5年、長期計画は5年以上が一般的で、どの企業も事業計画を作成した上で事業を展開していきます。
M&Aの実行後は、買い手が事業計画を引き継ぐことになるため、現段階での進捗や実現性、具体的なアクションなどをできるだけ詳細に記載するのが理想です。
また、事業計画は『バリュエーション』にも大きな影響を与えます。バリュエーションとは、適正な譲渡価格を算定するために、対象企業の価値をさまざまな手法を使って評価するプロセスです。
買い手は事業計画を基に将来性を評価したり、今後の事業戦略を考えたりします。
売却の理由
会社・事業を売却する理由は、経営者によってさまざまです。後継者不在でやむを得ず事業を手放す人もいれば、売却の利益を得て新たな事業にチャレンジしたい人もいるでしょう。
自社のさらなる発展を目指し、より資力のある第三者に経営を託したいと考えるオーナーも少なくありません。
『なぜこのタイミングで売却を選択するのか』を買い手に質問されることを想定し、売り手は理由や経緯を補足しておくのが望ましいといえます。買い手は売却理由を加味した上で、適切なM&Aスキームを選択します。




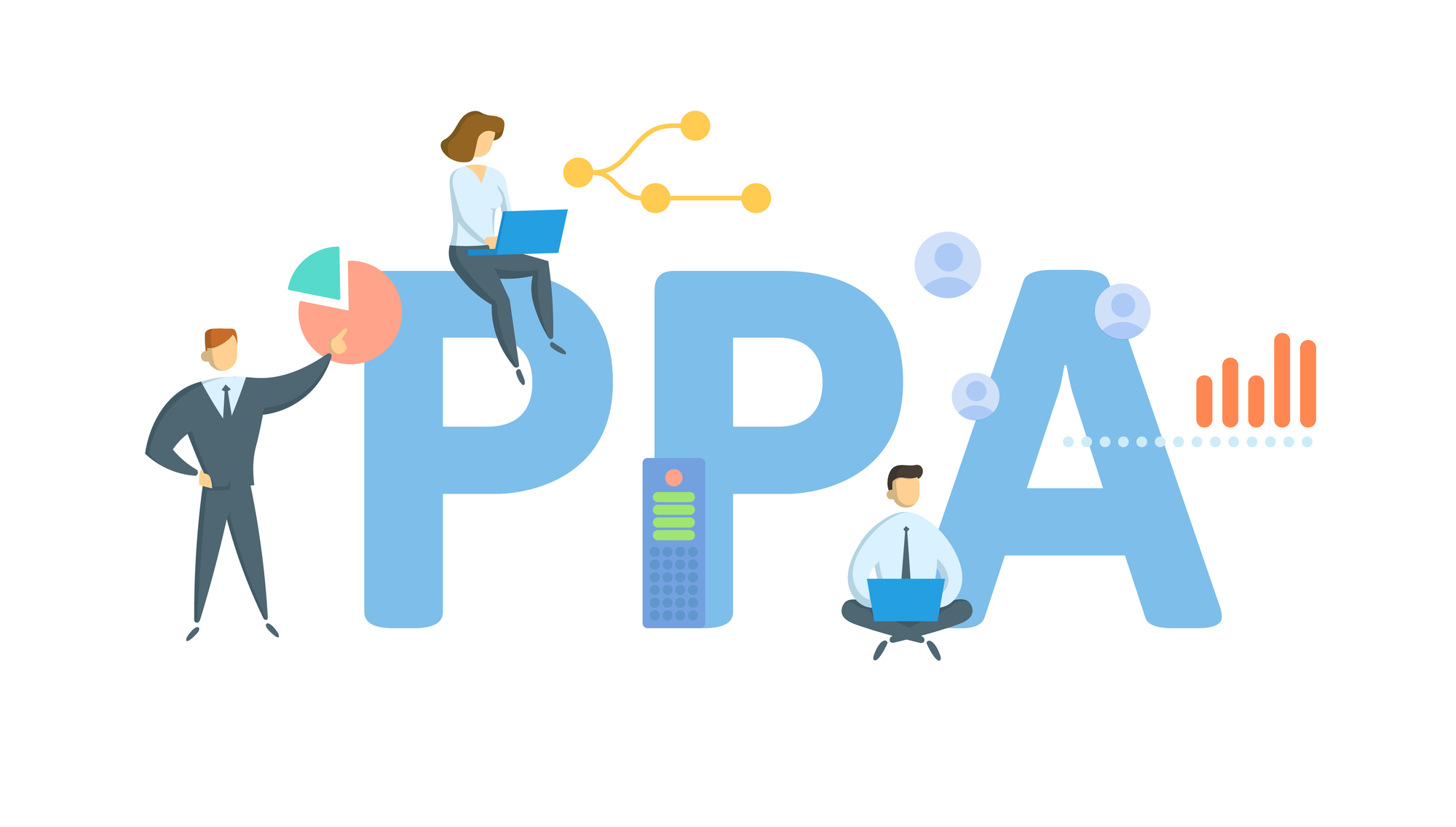
まとめ
M&Aにおいて、買い手はIMの情報をベースに、交渉段階に進むかどうか判断します。売り手にとってIMは単なる概要書ではなく、自社をアピールするために欠かせないものといえるでしょう。
IMの精度や見せ方によっては、M&Aが先に進まない可能性もあります。したがって、売り手はIMの作成に長けた優秀なM&Aアドバイザーを選定する必要があります。
一方の買い手は、IMの正確性が判断できる専門家にサポートを依頼するのが好ましいでしょう。財務データの数字の分析は、会計の知識を持った専門家の協力が必要です。
『TRANBI(トランビ)』は売り手と買い手をつなぐM&Aのプラットフォームです。サイト内では専門家の無料紹介を行っているほか、M&Aに関するさまざまな情報を公開しています。M&Aを考えている人は情報収集のためにご活用ください。







